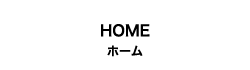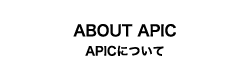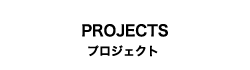西インド諸島大学モナ校学長招待計画

訪問期間中、医学分野では慶應義塾大学および東京大学医学部、民間企業の株式会社アルムを、工学分野では筑波大学、産業技術総合研究所(産総研)、パナソニックを訪れました。また、連携協定を締結している上智大学では、今後の教員レベルでの交流などについて意見交換が行われました。なお、各訪問先にはAPICの荒木事務局長・理事が同行しました。
今回のモナ校学長の招待により、2017年から開始された西インド諸島大学学長招待計画(モナ校〈ジャマイカ〉、ケーブヒル校〈バルバドス〉、セント・オーガスティン校〈トリニダード・トバゴ〉)がようやく実現しました。ただし、近年設立されたファイブ・アイランズ校(アンティグア・バーブーダ)については、今後の検討課題となっています。
◆APICでのオリエンテーション
一行は11月9日(日)に来日し、10日(月)午前中にAPICを訪問しました。重家理事長より歓迎の挨拶があり、日本の政治・経済・社会情勢および対外的な課題について説明が行われました。続いて荒木事務局長から、訪問先を含むプログラム内容およびAPICの対カリブ協力・支援活動の実績について説明がありました。
◆上智大学アイランド・サステナビリティ研究所 あん・まくどなるど教授との懇談
APICのオリエンテーション終了後、上智大学大学院地球環境学研究科教授であり、アイランド・サステナビリティ研究所所長のまくどなるど先生にご参加いただきました。まくどなるど先生より、アイランド・サステナビリティ研究所の活動について説明があり、また、UWI・APIC・上智大学の三者間の合意に基づき設立された奨学金制度の下で、UWIのケーブヒル校(バルバドス)から毎年1名の大学院生を受け入れていることが紹介されました。さらに、まくどなるど教授からはジャマイカからの学生も受け入れたい旨が述べられました。
◆株式会社アルム 訪問
11月10日(月)午後、渋谷にある株式会社アルム(Allm Inc.)を訪問し、相良美奈子執行役員(グローバル事業開発部部長)より同社の事業について説明を受けました。
同社は2022年にDeNAの連結子会社となり、遠隔医療支援ソリューション「Join Mobile Clinic」を提供しています。この「Join」は、院内システムと連携し、医療関係者がスマートフォンアプリや院内パソコンのWebブラウザーから場所を問わず医療情報を共有できるサービスです。加えて、医療機関や医療従事者向けに、院内業務の効率化や関係者間のコミュニケーション改善を支援する複数のサービスも提供しています。
医学部生の教育課題を抱えるUWI側はこのサービスに強い関心を示し、今後、同社とUWIとの間で連携に向けた協議を進めることとなりました。

11月10日(月)午後、日本工営株式会社を訪問しました。冒頭、望月鉄道技術本部鉄道計画部長より事業概要の説明があり、その後、担当者からジャマイカを含むカリブ諸国での主な事業について紹介がありました。
また、UWI側が首都キングストンでのLRT(ライトレールトランジット)開発に関心を持っていることを踏まえ、日本工営が世界各国で展開している鉄道事業に関するコンサルタント業務の概要についても説明がありました。
さらに、日本工営がカリブ海で環境問題となっているサルガッサ(サルガッサム:ホンダワラ属の褐色大型藻類で、2011 年以降カリブ地域等で爆発的な繫殖・漂着し、悪臭による環境汚染の他、観光業や漁業へも影響し、同地域の社会経済に打撃を与えている。)の利活用支援にも取り組んでいることが紹介され、UWI側からは今後の共同研究に向けて協力をお願いしたいとの発言がありました。
今後、日本工営側ではR&Dセンターがカウンターパートとなる予定です。

11月11日(火)午前、慶應義塾大学医学部を訪問しました。最初に、武林医学部長・衛生学公衆衛生学教授より、慶應義塾大学の創設者である福沢諭吉と、医学部の創設者である北里柴三郎という、大学にゆかりのある二人が新旧一万円札に描かれていることを紹介しつつ、慶應義塾大学および医学部の概要について説明がありました。続いて、ウイリアムズ学長からUWIモナ校の概要説明が行われました。
その後、南宮感染症学教室教授(感染制御部部長・臨床感染症センター長)より、慶應義塾大学医学部の6年間のカリキュラム構成(臨床医学、研究インターン、国家試験の時期など)について説明がありました。特に、海外研修に力を入れている点が紹介され、選抜された学生は、提携先である米国、欧州、アジア太平洋地域の大学病院で、短期の臨床見学や実習に参加できることが説明されました。
続いて、最近まで米国のジョンズ・ホプキンズ大学に数か月留学していた学生2名から、留学経験についての発表がありました。これを受けて、リード教授から交換留学の可能性について質問があり、慶應義塾大学側からは前向きに検討可能と回答され、今後、実現に向けて引き続き連絡を取り合うこととなりました。
その後の病院・キャンパスツアーでは、学生2名の案内により、構内を見学しました。

11月11日(火)午後、東京大学医学部を訪問しました。最初に、石原副研究科長より歓迎の挨拶と医学部の概要説明があり、続いてウイリアムズ学長からUWIの紹介が行われました。
その後、肝胆膵外科における臨床活動、泌尿器科領域の最新治療動向、リハビリテーション医学講座における教育・臨床・研究活動の概要、さらに看護学およびグローバル看護研究センターの取り組みについて、それぞれ担当教授よりパワーポイントを用いた説明がありました。
教員レベルでの連携については、東京大学側・UWI側の双方で検討可能との認識が共有され、今後の協議は東京大学国際交流室が窓口となって進められることとなりました。

11月12日(水)午前、筑波大学を訪問しました。最初に、筑波大学サンパウロオフィス副運営管理者の小金澤教授より、大学の概要について説明がありました。同オフィスは、筑波大学が2015年4月、ブラジル・サンパウロ大学キャンパス内に設置した拠点で、日本と中南米諸国との協力促進を図ることを目的としたグローバル戦略拠点です。筑波大学としてもカリブ地域の大学との連携を模索しており、今後、筑波大学側からUWIを訪問し、具体的な連携内容について協議を進めることとなりました。
続いて、同大学の「エンパワースタジオ」を視察しました。エンパワーメント情報学プログラムは、文部科学省の博士課程教育リーディングプログラムに採択され、2013年に発足した5年一貫の学位プログラムで、産官学を横断して活躍できるグローバルリーダーとなる博士学生の育成を目的としています。エンパワースタジオは、エンパワーメント情報学(人の機能の補完・協調・拡張によって生活の質を向上させることを目指す情報学)の実験施設で、広大な実験空間と前面のギャラリースペース(グランドギャラリー)から構成されています。
ウイリアムズ学長の視察時には、施設内の壁面全体に遠隔地で撮影した建物内部や町並みが投影され、見学者の動きに合わせて映像が変化する仕組みが紹介されました。まるで現場にいるかのような没入体験が可能で、遠隔地の課題をリアルタイムで把握できる最先端技術に、一行は強い関心を寄せていました。
その後、サイバニクス研究センターを訪問しました。「サイバニクス」とは、人・ロボット・情報系を中心に、脳・神経科学、行動科学、ロボット工学、情報技術(IT)、人工知能、システム統合技術、生理学、心理学、哲学、倫理、法学、経営など、異分野を融合した新たな学術領域です。同センターは、人とテクノロジー、そして社会が密接に結びついた国際的な研究開発拠点として位置づけられています。 訪問時には、人間の身体機能を拡張・補助する目的で開発されたロボットスーツHAL(Hybrid Assistive Limb)の着用デモンストレーションが行われ、学長一行は最先端の医療技術に非常に高い関心を示していました。

11月12日(水)午後、産総研を訪問しました。冒頭、企画本部国際部国際室総括主幹のKAZAOUI SAID(カザウィ・サイ)博士より、歓迎の挨拶と研究所の概要説明がありました。
経済産業省所管の産総研は、経済および社会の発展に資する科学技術の研究開発を総合的に進める、日本最大級の公的研究機関です。「社会課題の解決」と「日本の産業競争力強化」をミッションとし、全国12か所の研究拠点で多岐にわたる研究開発を展開しています。また、傘下の株式会社AIST Solutionsと一体となった産総研グループとして、世界最高水準の成果創出とその社会実装に力を入れているとのことでした。
産総研は、研究者2,287人、ポスドク等の契約研究者3,217人、企業派遣の客員研究員など5,896人、さらに事務系職員約900人の合計12,322人を擁する非常に大規模な研究機関であり、その規模に一同大変驚かされました。
続いて、「物を触らずに調べる」技術であるリモートセンシングについて説明を受けた後、常設展示施設「AIST-Cube」を見学しました。同施設は、“ちょっと先の未来”と出会える共創の場として設けられており、最先端の国立研究所の取り組みに一行は深い関心を寄せていました。

11月13日(木)午後、汐留にあるパナソニックのショールームを訪問しました。松下幸之助氏が電球の製造から事業を始めた創業の歴史に始まり、「National」から「Panasonic」へとブランドが変遷していく過程、そして高度経済成長期に普及したテレビ・冷蔵庫・洗濯機などの代表的な製品について、数多くの展示を見学しながら説明を受けました。
その後、同社が単なる家電メーカーにとどまらず、社会貢献型のサステナビリティを追求する企業へと進化していることについて、部屋いっぱいの大画面を用いたプレゼンテーションが行われました。続いて、自動搬送ロボット「ハコボ」のデモンストレーションも披露されました。
学長一行は、パナソニックのビジョンとミッションに強い感銘を受け、その日の理事長主催の夕食会でも、同社を訪問したことが話題に上りました。


◆上智大学 杉村美紀学長との会談
11月13日(木)午後、上智大学の杉村学長を表敬訪問しました。冒頭、杉村学長より温かい歓迎のご挨拶がありました。
続いてウイリアムズ学長から、安倍首相(当時)のジャマイカ訪問時に上智大学とUWIとの連携協定が締結されて以来、APICのご招待によりバルバドスのケーブヒル校やトリニダード・トバゴのセント・オーガスティン校の学長が訪日してきたこと、そして今回、自身がモナ校の学長として訪日する機会を得られたことに対し深い謝意が示されました。また、UWIの学生が毎年、学生招待計画を通じて上智大学にお世話になっていることにも感謝が述べられました。
これに対し杉村学長からは、UWIとの連携協定が早下学長(当時)によって締結された当時、自身は副学長としてその経緯をよく覚えていると述べられました。また、その後APICのご支援により、UWIとの関係がここまで発展してきたことに対し、大きな感謝が示されました。
その後の意見交換では、この連携協定に基づき、上智大学とUWIモナ校との間で教員レベルの交流を進めていく方向で両者の考えが一致し、今後、具体的な内容について検討を進めていくこととなりました。

11月13日(木)夜、ウイリアムズ学長一行の歓迎夕食会が如水会館にて開催されました。重家理事長の挨拶と乾杯の音頭で和やかに始まり、夕食会は終始和やかな雰囲気で進みました。最後にウイリアムズ学長より、今回の訪日招待に対する謝意と訪問が実り多いものであったとのスピーチがありました。
閉会にあたり、駐日大使としてのAPICのイベントへの出席が今回で最後となるリチャーズ駐日ジャマイカ大使から、これまでのAPICの支援に対する感謝の言葉が述べられました。

11月14日(金)、学長一行は朝8時30分発の新幹線で東京駅を出発し、京都を日帰りで訪れました。高台寺をはじめ、八坂の塔や祇園の町並みを車窓から眺めつつ、北野天満宮、紅葉苑、三十三間堂、金閣寺を巡り、秋の古都の風情を存分に堪能されました。
昼食には焼き鳥を味わい、帰りの新幹線ではビールを飲みながらゆっくりと過ごされたとのことです。
WHAT'S NEW
- 2026.1.15 EVENTS
第424回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2026.1.14 PROJECTS
インタビュー:田中一成 APIC常務理事(前駐マーシャル諸島共和国特命全権大使)を更新しました。
- 2026.1.14 SCHOLARSHIP
ザビエル奨学金卒業生のインタビュー記事が在パラオ日本国大使館のホームページに掲載を更新しました。
- 2025.12.18 EVENTS
第423回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2025.11.20 EVENTS
第422回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2025.11.19 EVENTS
西インド諸島大学モナ校学長招待計画を更新しました。
- 2025.10.23 INFORMATION
令和7年度事業計画書・収支予算書を更新しました。
- 2025.10.16 EVENTS
第421回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2025.10.16 EVENTS
太平洋・カリブ記者招待計画2025を更新しました。
- 2025.10.14 INFORMATION
役員一覧を更新しました。