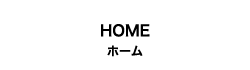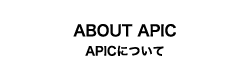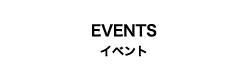「バルバドス 歴史の散歩道」(その4)
第3部 ピューリタン革命の荒波

(カーライル湾のビーチ風景)
(本稿は<一般社団法人>霞関会の2021年12月会報<No.908>に掲載された筆者の寄稿文「ピューリタン革命とバルバドス」に一部増補・訂正を加えたものです。)
カリブの島々をイギリスが植民地化しはじめた17世紀前半。北アメリカでも新しい動きを見ることができます。
1620年、現在の米国マサチューセッツ州東部にイギリス船「メイフラワー」号がたどり着きました。乗っていたのはプロテスタント・カルバン派のピューリタン(清教徒)の一団でした。当時のイギリスでは国王ジェームズ1世のもとでイギリス国教会が幅をきかせており、メイフラワー号に乗ったピューリタンたちは迫害を逃れて北アメリカにたどり着いたのでした。「ピルグリム・ファーザーズ」と呼ばれる彼らは裸一貫で入植し、プリマス植民地を建設します。
ちなみに、当時イギリスの商船隊がアジアの東端、日本にも到達していました。しかし日本では、イギリスはオランダとの貿易競争に敗れてしまいます。そのためイギリスが平戸の商館をたたんで日本から撤退したのが徳川家光が江戸幕府3代将軍となった1623年ですから、メイフラワー号が北アメリカに到達した少しあとのことです。
いっぽう、前に触れたようにバルバドスは1627年にイギリスの植民地となりましたが、まもなく狡猾なカーライル伯が植民地利権を手中におさめました。島では「悪代官」ハウリー総督が、ロンドンにいるカーライル伯の差し金によって入植者たちを重税で苦しめることとなります。ところが、10年にわたったハウリーの悪政が末期に近づいたころ、宗主国イギリスの国内が不穏な様相を見せ始めます。
*********************************************
<革命の勃発>
そのころジェームズ1世のあとを継いでイギリス国王となっていたのは、カーライル伯に言いくるめられてバルバドス植民地経営の特許状を与えた、あのチャールズ1世です。この王は、父王と同じように王権神授説を唱え、議会を無視する専制政治を行っていました。しかし、このころになると国教会体制に不満をもつピューリタンが国内でかなり力をつけていて議会でも影響力を増し、王党派と議会派の対立が深まっていました。
チャールズ1世は11年間も議会を開かずに独断専行の国政を続けていたのですが、長老派(プレビステリアン)が優勢だったスコットランドにイギリス国教を強制しようとしたため反乱が起きます。王はスコットランド反乱鎮圧の財源をまかなうためにやむなく議会を招集しました。ところが議会は戦費調達のための課税をこばみ、1642年、チャールズ1世に忠実な王党派と、オリバー・クロムウェルが率いる議会派の間に武力衝突が起きてイギリスは内乱状態に入りました。ピューリタン革命のはじまりです。
<ウィロウビー男爵、革命の渦中へ>
フランシス・ウィロウビー(1613-1666年)という人物がいました。イギリス、サッフォークの男爵の家柄の生まれです。成人すると父親のあとを継いで貴族院議員となりました。
ウィロウビー男爵は、ピューリタン革命がはじまると、いったんはクロムウェルに同調して議会派に加わりました。しかしまもなく、王政打倒も辞さない過激なクロムウェルに嫌気がさして、より穏健な長老派の議会リーダーのひとりとなります。このことがのちにウィロウビーをバルバドスに結びつけることにつながります。
ロンドンを占拠したクロムウェルはチャールズ1世を拘束して、あくまで立憲君主制の維持を望む長老派を議会から追放し、ウィロウビーも投獄されてしまいます。チャールズ1世は1649年、クロムウェルの議会派によって斬首されるという非業の死をとげました。王を失ったイギリスはしばらくの間、君主制が途絶え共和制の国となります。
いっぽうウィロウビーは財産を没収されたものの数ヶ月後に釈放されます。彼は故チャールズ1世の息子、チャールズ2世を奉じてオランダに亡命していた王党派に合流したあと、新天地を求め大西洋をわたってバルバドス植民地に向かいました。1650年のことです。
彼のバルバドス行きの背後には、島の植民地利権を握り、チャールズ2世一派のおぼえがめでたかった、ある人物がいました。その人物とは、例のカーライル伯の息子で、父の死後、バルバドス植民地利権を継承したカーライル伯2世です。国王と伯爵が、バルバドスつながりで親子2代にわたって結びついていたわけですが、彼らの側についたウィロウビーのバルバドス行きには次のような経緯があります。
ピューリタン革命が起きたあと、イギリス国内の混乱を逃れて王党派、議会派双方の人々が入植者として続々とバルバドスに渡ってきました。王党派のなかには貴族など上流階級の人々も多かったのですが、彼らは本国で失った財産を取り戻そうと、島の主要産業になりつつあった砂糖プランテーションの経営に力をそそぎました。プランテーションの労働力を確保するために西アフリカとカリブ地域の間では大西洋奴隷貿易が本格化していました。プランテーション経営に成功した者は砂糖の輸出で巨富を築き、本国様式の立派な邸宅を建てるようになります。バルバドスが「リトル・イングランド」と呼ばれはじめたのはこの頃のことです。
こうしてバルバドスでは王党派と議会派が混在していたのですが、はじめのうちは親元のイギリスと違って両派はわりあい仲良くやっていたようです。両派のあいだに「七面鳥とローストポークの誓約」という約束事がありました。これは「王党派」とか「議会派」という言葉を発した者は、罰としてそれを聞いたみんなを家に招いて七面鳥とローストポークを振る舞わなければならないという冗談半分の約束でした。ときにはわざと罰を受ける言葉を発して、両派一緒になってドンチャン騒ぎの「飲み会」を開くということもあったといわれます。
ところがチャールズ1世が処刑されてクロムウェルの軍事独裁がはじまると状況が一変します。迫害から逃れるために王党派が大挙してバルバドスに流れ込んだので、両派のあいだのバランスが崩れたのです。チャールズ1世を殉教者と仰ぐバルバドスの王党派は議会派の財産を没収するなど、議会派を露骨に圧迫するようになります。このときバルバドス王党派のリーダーだったのはハンフリー・ウォーロンド大佐という男でした。ウォーロンドはオランダに亡命していたチャールズ2世に忠誠を誓い、この王がバルバドスの君主であると宣言しました。
当時バルバドスではカーライル伯2世の息がかかったフィリップ・ベルという人物が植民地総督をつとめていました。ベル総督はバルバドス島内を、各地に点在するイギリス国教の教会を中心に11の教区(パリッシュ)に分けて治める制度(註1)を導入するなど手堅い実務家ではありました。しかし、王党・議会両派の抗争はベルの手にあまると考えたカーライル伯2世が、その手腕を見込んで送り込んだのがフランシス・ウィロウビーだったというわけです。バルバドスが産み出す富で暮らしていたカーライル伯2世にしてみれば、王党派とか議会派とかといったイデオロギー上の対立よりも、島に平穏を取り戻して収益を上げることのほうが優先だったのでしょう。
新総督となったウィロウビーはウォーロンド大佐を懐柔しながら両派のいざこざの火消しにつとめ、議会派の財産没収を帳消しにさせるなどの成果をあげました。
そればかりか彼はこの時期、バルバドスを起点として、カリブ海を南下して南米大陸の北東端にあるスリナムにちょっかいを出すということまでしています。スリナムにはイギリス人とオランダ人が入植していたのですが、ウィロウビーが派遣した武装船団はイギリス人入植者の中心地に砦を築きます。この砦は「ウィロウビー要塞」と名付けられました。これが現在のスリナムの首都パラマリボです(註2)。

(フランシス・ウィロウビー(当時の肖像画))
ところが一難去ってまた一難。今度はバルバドスにとって、もっと深刻な事態がもちあがります。宗主国であるイギリスの海軍艦隊がバルバドスに攻め込んできたのです。
どうしてそんなことになったのか。
王党派が優勢な、このちっぽけな植民地島のことをクロムウェル治下のイギリスが苦々しく思っていたのは当然です。しかし宗主国をキレさせた原因はもうひとつ別のところにありました。
それはバルバドスとオランダの関係でした。もともとイギリスによるバルバドスの植民地化当初は、バルバドスからタバコや綿花といった農産品をイギリスに運び、イギリスからは新たな移民や生活物資をバルバドスに運ぶという取引が行われていました。ところがピューリタン革命でイギリス国内が乱れると、イギリス・バルバドス間の交易が停滞します。そこに割ってはいったのがオランダでした。
オランダの提供する物資がイギリスよりも安かったこともあって、バルバドス・オランダ間の交易関係は急速に拡大しました。砂糖キビの栽培やプランテーションで働かせるためのアフリカ人奴隷の輸入を最初にバルバドスにもちかけたのもオランダです。
オランダは長年にわたってハプスブルグ家スペインの属領でしたが、16世紀後半にスペインから独立していく時期、急速に経済発展しました。中継貿易をつうじて世界各地に進出し、アムステルダムは国際金融の中心地となります。東インド会社を足場にしてアジアにも進出し、鎖国をはじめていた江戸幕府が、ヨーロッパ唯一の交易国として認めたオランダの商館を長崎の出島に設けたのが1641年ですから、ちょうどイギリスでピューリタン革命が起きるころです。
日の出の勢いのオランダと植民地バルバドスが結びつきを強めるのをイギリスは極度に嫌いました。
これまで見てきたように、カリブでのイギリスの植民地経営のやり方というのは、はじめから海軍の軍艦がひと様の土地や島に押しかけていって領土を奪うのではなく、富裕な貴族や商人が出資した武装商船が自らのリスクで乗り込んでいって、本国の承認を得たうえで「ここはイギリスの土地ということで決まり!」と宣言したのでした。そして先住民や奴隷を酷使して鉱物資源を採掘したりプランテーション経営をしたりして富を収奪し、本国はその上前をはねていたのです。
つまり「イギリス領土を名乗ってよい」という本国のお墨付きは、現代のコンビニチェーンのフランチャイズ制みたいなものだったわけです。ですからバルバドスがオランダと取引するのにイギリスが怒ったのも無理はありません。町のコンビニ店がフランチャイズ親会社の知らないところでライバル企業から勝手に商品を仕入れて儲けるようなものだったからです。
当時の西ヨーロッパは重商主義の時代。各国は戦費調達や軍、官僚組織の維持のために自国の輸出を最大化、輸入を最小化することによってひたすら富を貯めこもうとしていました。そのためにとられた方法は、競争国にイチャモンをつけてその産品にやたらと高い関税をかける、あるいはそもそも交易自体を禁じてしまうということでした。なにやら昨今の世界情勢を彷彿とさせるところ無きにしもあらずですが、このようなやり方の問題はしばしば競争国同士の戦争につながるということでした。
あちこちの植民地でバルバドスと同じようなことが起こっていたので、クロムウェル治下のイギリスは1651年、航海法を導入して植民地がオランダと取り引きすることをいっさい禁じてしまいます(註3)。今でいうデカップリングです。このことが後の英蘭戦争へとつながっていきました。
<イギリス艦隊のバルバドス討伐>
こうしたなかで半ば公然とオランダとの交易を続けるバルバドスに対し、宗主国イギリスがついに討伐のための海軍艦隊を差し向けたのでした。正規のイギリス海軍船がバルバドスに到達したのはこの時がはじめてです。艦隊を率いていたのはジョージ・エイスキューという提督でした。
迫ってくるエイスキュー艦隊を待ち受けるバルバドス総督ウィロウビーは、航海法を制定した本国の議会に対し「バルバドスが代表を送ってもいない議会が決めたことに従ういわれはない」と宣言して宗主国に反旗をひるがえしました。”聞いてない。クロムウェルごときが治める本国がナンボのもんじゃ”という心意気だったのでしょう。身のほど知らずのそしりは免れませんが、こういうふうにウィロウビーというのは相当とんがった男だったようです。
ウィロウビーはエイスキューの艦隊を迎え撃つために、首邑ブリッジタウンを擁するカーライル湾の沿岸やホールタウン、スパイツタウンといった要衝に民兵部隊を配備。オランダも武器や物資を供給してバルバドスを支援します。
カーライル湾に到達したエイスキュー艦隊は、湾に停泊していたオランダ商船隊を拿捕しました。しかしウィロウビーが海岸線にしいた布陣は歩兵6千、騎兵4百と強固なものでした。エイスキューはこの島を屈服させるのは容易ではないとみて、海上からバルバドスに降伏を呼びかけます。が、ウィロウビーは「国王以外の権威は認めない。我々は島を守る」と回答してはねつけました。ここにきてエイスキューは、海上を封鎖してバルバドスを兵糧攻めにする作戦に出ます。
小さな島は絶体絶命のピンチに立たされました。エイスキューはさらに隙をついて400人の兵士を上陸させてバルバドス側に大きな損害を与えます。これに動揺した島内の一部が寝返ってカーライル湾より東にあるオイスティンス港でエイスキューの部隊に合流してしまいました。
身内の造反でさすがのウィロウビーも和平交渉の席につくことに同意します。オイスティンスの宿屋「人魚荘(マーメイド・タバーン)」で行われた交渉のすえ、「バルバドス憲章」とよばれる和議が成立しました。
憲章の中身を見るとバルバドス側の無条件降伏というわけではなく、互いにかなり譲歩した形跡がみとめられます。憲章はバルバドス内で没収された議会派―つまりクロムウェル派―への財産の返還を保証するいっぽう、イギリス本国で財産を取り上げられていた王党派への財産返還も認めています。そのほかにも、信教の自由、バルバドス住民への課税にはバルバドス議会の同意が必要、議員は島内の土地所有者の選挙で選ぶ、そしてバルバドスの自由貿易を容認する(註4)など、当時としてはかなり進歩的な内容になっています。
バルバドス憲章は翌1652年にイギリス本国の議会でも承認されました。

(ジョージ・エイスキュ-(当時の肖像画))
もしウィロウビーが最後まで降伏せずにエイスキューの部隊と地上戦になっていたら、その後のバルバドスの歴史はずいぶんと違ったものになっていたかもしれません。「名誉ある降伏」を可能にしたウィロウビーはしかし、総督の地位を解任されてイギリスに帰国することとなります。後任の総督になったのは、ほかでもないエイスキューでした。
この時にウィロウビーが処刑も投獄もされなかったのが不思議なくらいなのですが、バルバドス憲章をよく読むと、ご丁寧にもウィロウビー個人の財産の保証や移動の自由までが書かれています。勝利した敵将エイスキューが「ジェントルマン精神」を発揮したのか、あるいはウィロウビーとエイスキューのあいだになんらかの取り引きがあったのか、そのへんは定かではありません。
けれどもイギリスに戻ったウィロウビーには、その後も平穏な暮らしがまっていたわけではありませんでした。クロムウェルは1653年に終身護国卿となって苛烈な軍事独裁体制をしきます。ウィロウビーは国内の権謀術数に巻き込まれて2度も投獄されています。
しかし、クロムウェルはその統治に民衆の不満が昂じるなか、1658年に病死。議会では長老派が勢いを盛りかえして、1660年には大陸に亡命していたチャールズ2世が呼び戻されて王政復古となり、イギリスは君主制の国に戻りました。
<ふたたびバルバドスへ>
ここでまたウィロウビーとバルバドスの縁が復活します。
大西洋をわたりバルバドスに戻った彼は、1663年、チャールズ2世によって再度バルバドス総督に任命されました。ところが、今度は落ち着いて島の統治に専念するかと思いきや、彼は総督の仕事を代理の者にまかせてしまい、バルバドスを起点にして近隣の島々への外征事業に取り組みはじめたのです。
まずは西隣のセントルシア島。この島は当時フランス領でしたが、ウィロウビーの船団はフランス駐屯地を攻略。「先住民が島をイギリスに売却することに同意した」という口実をでっち上げて島を奪いとってしまいました。(註5)
つぎに向かったのはオランダが占領していた南隣のトバゴ島です。ウィロウビーの船団がこの島に達すると、先乗りしていたロバート・サールというイギリス人の武装集団―おそらくは私掠船か海賊だったのでしょう―が島で略奪行為をはたらいているのに出くわします。ウィロウビーは乱暴狼藉をやめさせ、イギリス駐屯地を築いて引き揚げました。(註6)
<ウィロウビー、カリブ海に散る>
1666年7月28日、バルバドス総督ウィロウビー男爵は最後の航海に出ました。
今度は16隻の大船団に千人の兵士を乗せて、フランスにとられていた、北西かなり遠方のセントキッツ島(別名:セント・クリストファー島)を取り戻しに向かったのです(註7)。ウィロウビーは途中、フランス領グアドループ島を襲い商船2隻を拿捕します。ここからさき、さらにネービス島やアンティグア島で補給したあとセントキッツに攻めこむというのが彼の計画でした。
ところがセントキッツを目前にした8月4日夜、ウィロウビーの船団を悲劇が襲います。カリブでは毎年5月から11月のあいだはハリケーンシーズン。その真っ最中に船出した船団がハリケーンの直撃を受けたのです。多くの船が損害をうけ、ウィロウビーの乗った旗艦「ホープ号」は沈没。彼は船と運命をともにしてカリブ海の藻くずと消えたのでした。
貴族の家柄に生まれ、革命の渦中に身を投じ、バルバドスを舞台として大西洋とカリブ海を駆けめぐったフランシス・ウィロウビー。波乱に富んだこの男の生涯は、のちに世界の海を支配することとなるイギリスが、その興隆期に秘めていたエネルギーを象徴するもののひとつだったのではないでしょうか。
ウィロウビーは世を去りましたが、バルバドスはこのあと砂糖の輸出で大いに儲け、17世紀の末にジャマイカに取ってかわられるまでの間(註8)、イギリスのカリブ植民地のなかでも最も繁栄した島として、そしてそのダークサイドとして、カリブ奴隷貿易のハブとして知られるようになります。
*********************************************
ウィロウビーとエイスキューが対峙したカーライル湾。
ここには現在、ヒルトンやラディソンといったリゾートホテルや洒落たレストランが建ち並んでいます。海岸通りを内陸側にわたると首相府の建物があります。白砂のビーチには欧米からの多くの観光客がくつろぎ、セーリングやスキューバダイビングに興じる人々を見ることができます。
2019年のある日、筆者がカーライル湾沿いの、観光スポットから少し離れた小道をぶらぶら歩いていた時のこと。朽ち果てて雑草が生い茂った、かつてはさぞかし立派だったであろう石造りの館の痕跡があるのに気づきました。無人の館は分厚い石塀で囲まれているのですが、その石塀には、なにやら一列に穴が開けられています。よく見てみると、それは海の方角に向かって開けられた狭間(はざま=銃眼)ではありませんか。
宗主国イギリスの艦隊を迎え撃つウィロウビーたちが、バルバドス島を守ろうと、この狭間から眼前の青く澄んだカリブ海に向けて鉄砲を構えていたのかもしれません。
(第4部「海賊たちの系譜」に続く)

(ウィロウビーがフランスから奪ったセントルシア島。遠くに見える「双子の山」、ピトン山は2004年にユネスコ世界遺産に登録されました。)
(註2)イギリスとオランダはスリナムの領有権をめぐって争いましたが、1667年のブレダ条約でオランダが北アメリカのニューアムステルダム(現ニューヨーク)をイギリスにゆずり、かわりにスリナムがオランダに帰属することとなってオランダ領ギアナとなります。スリナムは1975年にオランダから独立。
(註3)歴史家ロバート・ショムバーグが1848年に著したバルバドス史の古典「バルバドスの歴史」には次のような記述があります。「もし世界の海をイギリスが支配することを航海法が導いたのだとしたら、その航海法に導く原因となったのは、あの小さな島(バルバドス)だった」
(註4)このバルバドス憲章のなかの自由貿易の条項には「イギリスと友好関係にある国(との自由貿易を認める)」という但し書きがあります。つまり、航海法の標的になっていたオランダはバルバドス自由貿易の対象国から除外されていました。
(註5)セントルシアをめぐってはイギリスとフランスが争奪戦を繰りひろげ、最終的にナポレオン戦争後の1814年にパリ条約でイギリスの領有が確定するまで14回も領有権が入れ替わりました。のち1979年にイギリスから独立。
(註6)トバゴ島の事情はセントルシア島よりもさらに複雑で、いくつかの国の間で31回領有権が変わっています。結局セントルシアとおなじく、1814年に隣のトリニダード島とともにイギリス領となり、1962年にトリニダード・トバゴとして独立。ちなみに、トバゴ島を奪い合っていた国にはイギリス、フランス、オランダといった列強にくわえ、バルト海沿岸の「クールラント公国」(現ラトビアの一部)という国がありました。クールラントは17世紀後半の数十年間この島を領有。島は「ニュークールラント」とよばれ、新大陸で最小の植民地だったといわれています。
(註7)セントキッツ島もイギリスとフランスのあいだで領有が何度も入れ替わりました。ヨーロッパ中を巻き込んだスペイン継承戦争の平和条約(ユトレヒト条約)で1713年にいったんイギリス領として確定します。1782年フランスが再度襲撃しましたが、翌年のベルサイユ条約(このベルサイユ条約は、イギリス、フランス、スペインのあいだで結ばれたアメリカ独立戦争の講和条約)でイギリスに返還されました。1983年、南隣のネービス島とともにセントキッツ・ネービスとしてイギリスから独立。
(註8)当初スペイン領だったジャマイカは1655年にイギリスが奪って以降急速に開拓が進み、17世紀末になると砂糖生産でバルバドスをしのぐようになります。
(本稿は筆者の個人的な見解をまとめたものであり、筆者が属する組織の見解を示すものではありません。)
WHAT'S NEW
- 2026.1.15 EVENTS
第424回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2026.1.14 PROJECTS
インタビュー:田中一成 APIC常務理事(前駐マーシャル諸島共和国特命全権大使)を更新しました。
- 2026.1.14 SCHOLARSHIP
ザビエル奨学金卒業生のインタビュー記事が在パラオ日本国大使館のホームページに掲載を更新しました。
- 2025.12.18 EVENTS
第423回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2025.11.20 EVENTS
第422回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2025.11.19 EVENTS
西インド諸島大学モナ校学長招待計画を更新しました。
- 2025.10.23 INFORMATION
令和7年度事業計画書・収支予算書を更新しました。
- 2025.10.16 EVENTS
第421回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2025.10.16 EVENTS
太平洋・カリブ記者招待計画2025を更新しました。
- 2025.10.14 INFORMATION
役員一覧を更新しました。