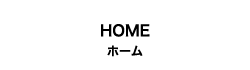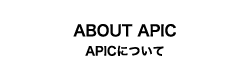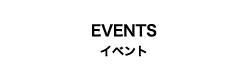「バルバドス 歴史の散歩道」(その18)(最終回)
第10部 独立後の歩み

(超音速旅客機 コンコルド)
その“怪鳥”がバルバドスにはじめて姿をあらわしたのは1977年11月2日のことでした。
この日、在位25周年記念の各国歴訪の最終訪問地バルバドスからイギリスに帰国するエリザベス2世女王(当時)夫妻を迎えに、超音速旅客機「コンコルド」の特別機がグラントリー・アダムス国際空港に降りたったのです。マッハ2を超える速度のコンコルドは、女王夫妻をわずか3時間半で大西洋をへだてたロンドンに連れて帰りました。
10年後、1987年12月にはロンドン・バルバドス間に週1便のコンコルド定期運航が開始されています。イギリスとフランスが共同開発したコンコルドの定期便が発着していたのは当時世界中でバルバドスのほかは、ロンドン、パリ、ニューヨーク、ワシントンDC、ダラス、バーレーン、シンガポール、ダカール、リオデジャネイロのみでした。
その後、コンコルドは機体の老朽化や2001年の9・11事件で観光需要が一時大幅に落ち込んだことなどにより2003年に引退。バルバドス便も終了したのですが、コンコルドのロンドン・バルバドス便が15年以上にわたり就航していたことは、この島がイギリス人、とりわけ富裕層のバカンス地として高い人気を誇っていたことを物語っています。
独立後のバルバドスは、衰退する砂糖産業にかわって観光を主産業とする安定した国として成長してきました。しかし本稿でこれまで述べてきたように、平和なこの島も外敵の脅威で存亡の危機に瀕したことが幾度かありました。そしてなによりも、イギリスによる植民地支配の下での非人間的な奴隷制という過酷な体験ををくぐり抜けてきた歴史があります。
こういう歴史をもつ国々の中には、バルバドス周辺のカリブ諸国もふくめ、独立してから政情が安定せず治安にも問題があるという国がままあります。けれども、バルバドスは独立以来これまで、クーデターや暴力的な政変を経験したことは一度もありません。また、周辺のカリブ諸国と比べて治安も良く、これもバルバドスが観光立国に成功した大きな要因であるといえます(註1)。
この最終章では、独立後、現在にいたるまでのバルバドスの歩みを見ていきたいと思います。
*********************************************
<初代首相バーロウの功績>
バルバドス独立後の初代首相となった民主労働党(DLP)党首・エロール・バーロウは、1976年まで2期10年にわたってその地位にありました。
バーロウは、内政面では健康保険制度の整備、選挙権の18歳への引き下げ、砂糖産業労働者の待遇改善といった政策を実行して、新しい国の安定的発展の土台作りに力をそそぎました。また、教育の重要さを認識していた彼は、すでに無償化されていた初等教育にくわえて中等教育の無償化を実現します。英語圏カリブ諸国が共同で運営する西インド諸島大学(UWI)のバルバドス校(ケーブヒル・キャンパス )や、バルバドス独自の成人教育機関「バルバドス・コミュニティ・カレッジ」が設立されたのもバーロウの首相在任中です。
外政面での彼の大きな功績は、カリブの地域統合への動きの推進役となったことです。独立を目前にひかえた1965年、バーロウは、かつてロンドンでともに学んだイギリス領ギアナ(現ガイアナ)の指導者フォーブス・バーナムと、ふたつの領域間での貿易自由化に向けた話し合いをはじめました。この構想にアンティグアとトリニダード・トバゴがくわわって68年5月に発足したのが「カリフタ(CARIFTA - カリブ自由貿易連盟)」です。カリフタにはその後、ドミニカ、グレナダ、ジャマイカ、セントルシア、ベリーズほかが参加し、英語圏カリブの多くの国・地域を包含する組織となります。
カリフタの関連機関として1970年にカリブ開発銀行(CDB)が設立された際、バーロウはCDB本部をバルバドスに誘致することに成功しています。
カリフタがさらに発展したのがカリコム(CARICOM - カリブ共同体)です。カリコムは、バルバドス、ガイアナ、ジャマイカ、トリニダード・トバゴという4ヵ国を原加盟国として、地域の経済統合、外交政策の調整、保健医療・教育などに関する協力の促進を目的に1973年7月のチャガラマス条約で設立された地域機構です。カリコムの発足によりカリフタは発展的に解消され、カリブ開発銀行もカリコム関連機関となります。カリコムは現在では14ヵ国・1地域が加盟する地域機関に成長しています(註2)。
カリフタ、そしてカリコムは自由貿易や経済統合、政策調整をめざす地域機構であって国家連合ではありません。しかし、かつての「西インド諸島連邦」や「東カリブ連邦」の試みにみられたような、グラントリー・アダムス、エロール・バーロウなど西インド諸島の旧イギリス植民地の指導者たちが希求していた地域の連帯をある程度まで体現した取組みであると言えるでしょう。

(ブリッジタウンの独立広場に立つエロール・バーロウの銅像)
バーロウが首相をつとめていた時代は、バルバドスの観光産業が急速に成長した時期でもありました。
旧宗主国イギリスの人々が、バルバドスを金儲けのための砂糖キビ・プランテーションの島としてだけでなく、観光地としても認識するようになったのは20世紀初めくらいからのことです。ただ、その頃は航空機を使っての旅行というのはまだ夢のような話だったので、旅行者は汽船で大西洋を渡っていました。避寒地バルバドスでのバケーションを楽しめたのはカネと時間をもてあますごく一部の富裕層に限られていたのです。
首都ブリッジタウンの東16kmにあるシーウェル空港(のちのグラントリー・アダムス国際空港)を発着する空路の定期便が普及しはじめたのは第二次大戦後のことです。1952年の記録を見ると、バルバドスへの海路での年間入国者数は5,415人、空路では15,510人となっており、クルーズ船観光がまだ盛んでなかった当時は空路入国者が海路のそれを大幅に上回っていたことがわかります。
ちょうどバルバドスが独立した1966年にカーライル湾南端のニーダムス・ポイントにヒルトン・ホテルが開業したのは象徴的な出来事でした。その後、島の南海岸と西海岸を中心に外資系のリゾートホテルが次々と進出し、欧米からの比較的安価なパックツアーの普及もあって、観光立国が軌道に乗るようになります。衰退しつつある砂糖産業にかわり観光産業がこの島の経済を支えるようになっていったのです。
空路観光客の伸びにくわえ、カリブ海を周遊する大型クルーズ船の定期運航が盛んになると海路旅行客数も順調な伸びを見せるようになります。バルバドスがカリブ海クルーズの主要拠点のひとつとなることができたのは、複数の大型クルーズ船や貨物船が停泊することができる現在のブリッジタウン港“ディープウォーター・ハーバー”が独立前の1961年にすでに完成していたからです。
ディープウォーター・ハーバー建設は、当時バルバドス植民地自治政府首相であったグラントリー・アダムスの功績です。将来の独立と経済発展を視野に入れて近代的な港湾を整備したのはアダムスの先見の明だったといえるでしょう。
バルバドス独立前の困難な時期に宗主国イギリスの思惑とも歩調をあわせながら政党政治を根づかせ、アフリカ系住民を主役とする自治を拡大していったグラントリー・アダムスは、エロール・バーロウが「独立の父」と呼ばれるのに対し、しばしば「民主主義の父」と称されます。
アダムスは独立後も野党指導者として隠然たる影響力を保持していたのですが、しだいに健康を害し、1971年11月28日、73歳で世を去りました。彼は、11人いる「バルバドス国民英雄」にその名を連ねています。
<バーロウ敗れる>
労働者の権利を重視する社会民主主義色が強い政策と観光産業へのテコ入れで独立直後のバルバドスを軟着陸にみちびいたバーロウ政権も、2期目の後半、1970年代なかばに入ると勢いを失ってきます。
70年代、欧米諸国の経済は停滞期にありました。通貨危機、石油危機などがかさなって成長が鈍化します。とくに観光客数をふくめバルバドスの最大の経済パートナーだった旧宗主国イギリスは「英国病」と呼ばれる深刻な社会・経済の不振に陥っていました。
外的影響にさらされやすい小国バルバドスでは景気が後退。成長は頭打ちになり失業率が上昇します。バーロウ政権はさらに、裁判官任命に関する法改正をめぐり世論の批判もあびていました。
このような中で実施された1976年の総選挙で、バーロウを党首とする民主労働党(DLP)がライバルのバルバドス労働党(BLP)に敗北し、独立以来10年のあいだ政権をになってきたバーロウとDLPは野に下ることとなります。
バーロウにかわって第2代首相となったのは、あのグラントリー・アダムスの子息、トム・アダムスでした。

(第2代首相 トム・アダムス)
トム・アダムス(1931〜85年)の本名は「ジョン=マイケル=ジェフリー=マニンガム・アダムス」というえらく長い名前だったのですが、大人になってからも子供時代からの愛称で「トム」と呼ばれていて、政治家としても通常この名で呼ばれています。
父グラントリーと母グレースの一人息子だったトムは、父と同様に島の名門ハリソン・カレッジを経てイギリス・オクスフォード大学で学び弁護士資格をとります。そして、BBC(イギリス放送協会)などで働いたあと、1962年、31歳の時にバルバドスに戻るとすぐ、父が党首をつとめていたBLPの幹部となりました。バルバドス独立4年前のこの時期、BLPは野党に転落しグラントリー・アダムスも無役となっていたので、若き“サラブレッド”、トムが島にもどって党勢の回復に取り組むことになったわけです。
トムは、1965年の総選挙で当選して下院議員となります。父グラントリーが71年に亡くなるとトムが野党リーダーの座を引き継ぎ、そして76年総選挙で彼のBLPがバーロウのDLPに勝利した結果、独立後第2代目の首相となったのです。
ふりかえってみると、バルバドスの独立プロセスというのは、独立前の長いあいだ老練なグラントリー・アダムスが丹念にパン生地をこね、独立までもう一歩というところで一世代若いエロール・バーロウがそのパン生地をかすめ取って見事にパンを焼き上げた、という流れだったともいえます。その意味では、バーロウから政権を奪還したトムは父グラントリーの無念の雪辱を果たしたともいえるでしょう。
<グレナダ侵攻>
トム・アダムスの率いるBLPは1981年の選挙でもDLPに勝利して、彼は首相として2期目に入ります。
おなじ年、アメリカではロナルド・レーガンが大統領に就任しました。バルバドスがアメリカに追随するかたちで、軍事目的での海外派兵をおこなったのはこのレーガン政権のときでした。
アメリカとソビエト連邦を両極とする東西冷戦が厳しさを増していた当時、トム・アダムス政権のバルバドスほか英語圏カリブ諸国のいくつかは、外交面で反共・新保守主義的路線をとるアメリカのレーガン政権に協調する立場をとっていました。
ところが、バルバドス南西の隣国グレナダでは1974年の独立以降、政情が安定せず、79年にクーデターでモーリス・ビショップを首班とする左翼政権が成立。ビショップ政権はキューバに接近し軍事援助を受けるようになります。
アメリカにとってカリブでの悪夢は「第2のキューバ」が出現することです。1982年、アメリカの主導でカリブの「地域安全保障システム(RSS)」が設立され、バルバドスは東カリブ諸国機構(OECS)(註3)の4カ国 -- アンティグア・バーブーダ、ドミニカ国、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島 -- とともにRSSに加わりました。RSSの当初の目的がカリブでの共産主義勢力の拡大防止にあり、直接的な契機がグレナダの状況だったことは明らかです。
グレナダ介入の機会をうかがっていたアメリカは、1983年10月にグレナダ政府内で親ソ連派が再クーデターを起こしてビショップ首相が殺害され国内に混乱が生じたのをとらえ、「グレナダ国内の米国民の安全を確保する」ことを理由として行動にでました。まずグレナダを空爆したあと約7000人の海兵隊を人口10万足らずのこの島国に上陸させ、親ソビエト政権を潰しにかかったのです。侵攻作戦は、CIA長官を経てレーガン政権で副大統領をつとめていたジョージ・ブッシュ(父)をヘッドとするチームにより策定されたものでした。
グレナダ侵攻は小規模であったとはいえ、ベトナム戦争敗北後のアメリカが再び本格的に外国に武力介入したはじめてのケースです。このとき、トム・アダムス政権下のバルバドスが、ジャマイカおよびOECS諸国とともにアメリカを支援するためにグレナダに兵力を派遣したのです。東カリブ地域における共産主義の伸張をおそれたトム・アダムスは、アメリカに協力して軍を派遣する必要性について周辺諸国を熱心に説いたといわれます。
じつは、バルバドスの海外派兵はグレナダが最初ではなく、バルバドスの西隣りに位置し1979年12月に独立したばかりのセントビンセント及びグレナディーン諸島(以下:セントビンセント)に小規模な派兵をしたことがあります。
グレナディーン諸島を構成する小さな島のひとつ、ユニオン島では経済的困窮による島民の不満が高まっていました。ユニオン島の一部住民が、すぐ南隣りの国、グレナダで同年3月に起きたクーデターで左翼政権ができたことに刺激を受けて12月に武装蜂起を起こしたのです。
ミルトン・ケイトー・セントビンセント首相は非常事態宣言を出し、アメリカ、イギリス、周辺のカリブ諸国に蜂起制圧のための応援を要請。唯一この呼びかけに応じたバルバドスのトム・アダムス首相が少人数の部隊を派遣しました。蜂起はすぐに鎮圧され大ごとにはならなかったのですが、グレナダ左翼政権の影響が国境をこえてあやうく他国に波及しかけたケースでした。アメリカがいくつかのカリブ諸国を連れてグレナダに侵攻したのはこの4年後です。
さて、グレナダ侵攻に際してバルバドスほかのカリブ諸国が出した兵員数は合わせてわずか300人程度というシンボリックなものでした。これは、アメリカにとっては、単独介入による国際世論の非難をかわすため自己の影響下にあるカリブ諸国を利用して「多国籍軍」の体裁をととのえる必要があっただけで、べつに彼らの軍事力を頼りにしていたわけではなかったからです。
とはいえ、侵攻に際してアメリカは、グレナダから北東260kmのところにあるバルバドスのグラントリー・アダムス国際空港を爆撃機の基地として、そしてディープウォーター・ハーバーを軍艦船の基地として使ったので、アメリカから見ればこの島はかなり役にたったといえます。これは、かつてバルバドスがイギリス植民地だった時代にイギリスが周辺の東カリブの島々を攻略する際の拠点として使われていた過去を想起させます。
グレナダ侵攻以降、バルバドスは自然災害救援活動などをのぞき他国に軍を派遣したことはありません。けれどもグレナダの前例は、もしも将来おなじような事態が周辺で起きた場合にバルバドスが置かれることになるかもしれない戦略的な位置づけを暗示しているとも言えます。
グレナダ軍はアメリカ・カリブ連合軍の侵攻に対し、駐留していたキューバ兵やソ連、東ドイツ、北朝鮮などの軍事顧問の支援を受けて応戦したものの、わずか数日のうちに制圧されました。戦闘では、民間人含め双方で100人近い死者(うちアメリカ軍は19人)、500人以上の負傷者が出ています。この侵攻でグレナダの親ソ政権は崩壊し親米政権が樹立されました。翌1984年にはレーガン大統領がこの島を凱旋訪問しています。
グレナダ侵攻は短期間で終了したものの、カリコム内ではアメリカの作戦に加わったバルバドスほかの国々と、グレナダの主権尊重の立場から加わらなかったトリニダード・トバゴ、ガイアナ、バハマ、ベリーズなどの国々のあいだに論争が起き、一時は険悪な雰囲気になりました。
<トムの死。バーロウ復活するも・・・>
このように外交・軍事面ではレーガン政権寄りの政策をとり、国内ではハイウェイ網の拡張などインフラ整備に力を入れていたトム・アダムスでしたが、彼は首相2期目の末期、1985年3月11日に執務室で心臓発作を起こして倒れ帰らぬ人となってしまいました。53歳という若さで、前日まで元気だった彼の突然の死に国民がショックを受けたのは言うまでもありません。
彼の逝去後、副首相だったハロルド=バーナード・セントジョンが首相のあとを継いだのですが、翌86年の総選挙でトムなきBLPはDLPに大敗してしまいます。新首相となったのはエロール・バーロウでした。野党DLP党首として捲土重来を期していた独立後の初代首相バーロウが10年ぶりに首相の座に返り咲いたのです。
トム・アダムスとちがってバーロウは、グレナダ侵攻にはきわめて批判的な立場をとっていて、レーガン大統領のこともあまり好きではなかったようです。バーロウは、10年ぶりの首相ポストへの復帰に際する記者会見でレーガンのことを「ホワイトハウスのカウボーイ」呼ばわりし、在バルバドス・アメリカ大使館から抗議を受けています。(この顛末について、“バーロウは抗議してきたアメリカ大使館に対して『もっとひどい言葉』を使って言い返した”という都市伝説が語り継がれています・・・。)
トム・アダムス政権時代にアメリカ主導で設立されバルバドスも加盟していたRSS(地域安全保障システム)にもバーロウは懐疑的で、RSSがしばしばプエルトリコで軍事演習をおこなっていたことについて、こう述べています。
「カリブが平和の地域として認識され尊重されねばならないという私の立場は変わらない・・・プエルトリコはこの地域の新植民地化のための発射台となってしまった。私たちは、プエルトリコがたびかさなる軍事演習で基地として利用されているのを目のあたりにしている。軍事演習の目的は明らかである・・・繰り返して言うが、私がバルバドスの首相であるあいだは、我が国の領土が近隣国を脅迫するために使われることはない。その近隣国がキューバであろうとアメリカであろうとにかかわらずだ」
といっても、バーロウはあくまで議会制民主主義と市場経済の信奉者であって、けっして共産主義のシンパだったのではありません。彼はただ、東側であろうが西側であろうが大国の押し付けに唯々諾々と従うことをよしとしない「誇り高きカリブ民族主義者」だったのです。
そのことをよく示す1986年の彼のスピーチの抜粋。
「カリブ地域を米国の潜在的問題だとみるのは非人間的であり虚偽である。私たちには自己のアイデンティティーと文化と歴史がある。バルバドス議会は1989年には創立350周年を迎える。民主主義について誰の説教も受ける必要はないのである。カリブ地域がいかなる経済困難に直面しようとも、私たちの社会は問題を理解し克服するに足る知的・制度的な手段をもってそれを乗り越えて機能する社会なのだ」
カリブを「みずからの権益を守るためのバックヤード(裏庭)」として扱おうとするアメリカに対し、バーロウは、“よけいなお世話だ、ほっといてくれ”と言ったわけです。この意味で、レーガンに対しても歯に衣を着せぬほど反骨精神旺盛だった彼は、東西冷戦構造のなかで非同盟主義的な志向を強くもっていた人物と言えるでしょう。
ただアメリカにしてみれば、親米的だった前任首相のトム・アダムスとの対比で、バーロウが目ざわりな存在になっていたとしても不思議はありません。もしもバーロウの政権が長続きしていたら、その後のバルバドスの国際社会での立ち位置は、良い悪いはさておき、現在とやや違ったものになっていたかもしれません。
「もしも・・」と書いたのは、バーロウは首相に返り咲いてわずか1年後に突然死しまったからなのです。1987年6月1日、彼が67歳の時でした。死因は「急性心不全」とされています。
バーロウの遺灰は、生前のこしていた自身の言葉にしたがってカリブ海にまかれました。彼の誕生日、1月21日(1920年)は毎年「エロール・バーロウ・デー」として国民の祝日となっており、また彼はのちに「バルバドス国民英雄」のひとりに列せられました。
バーロウ亡きあと、バルバドス外交はふたたび親米路線に回帰しています。
<安定の理由>
「民主主義の父」グラントリー・アダムスが亡くなり、そしてその息子トム・アダムスと「独立の父」エロール・バーロウの両人ががわずか1年ほどの間にともに突然世を去ったことで、独立後のバルバドスのひとつの時代が終わりました。
その後こんにちまで、この国ではバルバドス労働党(BLP)と民主労働党(DLP)の2大政党が選挙により交代して政権を担ってきています。
1987年 エロール・バーロウ首相逝去によりDLPのロイド=アースキン・サンディフォード首相就任
1991年 総選挙でDLP政権継続。サンディフォード首相再任
1994年 議会で不信任決議案を出されたサンディフォード首相が議会を解散。総選挙でBLPが政権奪還しBLPのオーエン・アーサー首相就任
1999年 総選挙でBLP政権継続。アーサー首相再任
2003年 総選挙でBLP政権ふたたび継続。アーサー首相再々任
2008年 総選挙でDLPが政権奪還。DLPのデービッド・トンプソン首相就任
2010年 トンプソン首相逝去によりDLPのフロンデル・スチュアート首相就任
2013年 総選挙でDLP政権継続。スチュアート首相再任
2018年 総選挙でBLPが政権奪還。BLPのミア・モトリー首相就任
2021年 共和制に移行。サンドラ・メイソン初代大統領就任
2022年 共和制移行後の前倒し総選挙でBLP政権継続。モトリー首相再任
このように、おおむね2期・10年ごとに政権交代が起きています。民主主義の擁護者を自認するどこかの大国と違い、選挙結果をめぐって見苦しいののしり合いや訴訟沙汰が起きたり、ましてや議会への暴徒乱入事件が発生したりしたこともなく、政権はスムーズに移譲されてきました。筆者はバルバドス在勤中に2度(2018年、2022年)の総選挙を目撃しましたが、選挙キャンペーンから投票結果確定、新内閣成立にいたるまでのプロセスは、拍子抜けするほど整然としたものだったと記憶しています。
このように秩序だった政権交代がバルバドスで続いてきたのは、植民地時代から培われてきた議会政治の伝統や政治活動・言論の自由が根付いていることのほか、近年ではBLPとDLPの間にイデオロギー上の差異がほとんどなくなっていることも関係していると思われます。ある程度の政権担当期間をへて与党に疲れが見えたり顔ぶれがマンネリ化してくると、変化を求める有権者の期待が政権交代につながるというのがパターン化しているのです。
それに加え筆者としては、バルバドスが政治的に安定している理由のひとつとして、民族的な同質性が高いことも関係しているという気がしています。これはバルバドスとおなじく英語圏カリブに属しながらも、国内でアフリカ系とインド系の数が拮抗しているトリニダード・トバゴやガイアナと対照的です。これらの国では、対立する主要政党が事実上アフリカ系とインド系の利益を代弁する民族政党となっているため国内政治は常に緊張をはらんでいます。
トリニダード・トバゴやガイアナは、19世紀の奴隷制廃止以後、アフリカ系労働力を補完するために世界各地のイギリス支配地域からインド系、アラブ系、中国系、とりわけ多くのインド系の人びとが移民してきたという過去をもっています。いっぽう労働市場が小さかったバルバドスではこういう現象はほんのわずかしか起きませんでした。
バルバドスでは現在も人口のおよそ95%をアフリカ系が占めていて、民族的バックグラウンドによる政治対立はありません。昨今、“多様性(ダイバーシティ)”とやらが世界中で無闇やたらともてはやされていて日本も例外ではないようですが、「小ぶりで同質性が高いことがバルバドスの強みだ」と言ったら不適切にもほどがあるでしょうか?
<世界に向けて発信するミア・モトリー首相>
筆者が日本大使としてバルバドスに着任したのは2016年10月のことでした。当時はフロンデル・スチュアートを首相とするDLP(民主労働党)政権の時代。2期8年目に入っていたDLP政権には疲れが見えていて、2008年の世界金融危機による負の影響に対し政府がタイムリーな方策をうち出せずにいたため貿易赤字、公的債務が増大し、成長や雇用もかんばしくなくなっていたこともあって、国民のDLP離れが急速に進んでいました。
2018年5月に政権交代が起きます。総選挙でミア・モトリーが率いるBLP(バルバドス労働党)が得票率73%で下院の全30議席全てを獲得するという、前例のない圧勝をおさめたのです。
1965年生まれのミア・モトリーは、祖父の代から政治家、法律家などを輩出したバルバドスの名門一族の出身です。彼女はロンドン・スクール・オブ・エコノミクスを卒業してまもなくバルバドス政界入りし、早くも94年には29歳の若さでオーエン・アーサーBLP政権の教育大臣に起用されています。その後、与野党・政府の要職をへて、2018年にBLPが政権に返り咲いたときにバルバドス初の女性首相となりました。
モトリーは首相に就任するとただちに経済の立て直しに取り組みます。IMF(国際通貨基金)との間で債務再編協議を開始し、拡大信用供与(EFF)について合意し長期融資を得ました。国内的には、赤字続きの国営企業の合理化などをふくむ荒療治ともいえる経済改革プログラムを実施していきます。筆者はブリッジタウンにいてこれを間近に観察していたのですが、小さい国では特効薬が効きやすいとはいえ、これほど早く経済改革の効果が出るものなのかと驚きながら見ていました。
ところが、バルバドス経済が目にみえて上向きになってきた時に始まったのが、あの新型コロナ感染症の世界的な流行です。当然ながら頼みの観光業は大打撃を受けることになりました。「この小さな島でコロナが大流行したらえらいことになるから国境を閉ざすのだろうな。休暇帰国もダメか・・」と筆者は観念しました。たしかに近隣のカリブ諸国はどこも鎖国に近いような厳しい出入国制限をとりました(トリニダード・トバゴなどは自国民の帰国すら禁止しました)。
けれどもバルバドスは違っていました。モトリー首相は、パンデミック当初こそロックダウン策を講じたものの、外国人の来訪を極限まで制限しつづけたほうがよいのではという国内の慎重論も強いなか「観光で生きるこの国が門戸を完全に閉ざすのは致命傷になる」と言って頑としてゆずらず、各国航空会社に乗り入れ禁止や便数制限を命じるのでなく逆に定期運航便の維持を要請しました。
そればかりか、コロナ流入を恐れる近隣諸国の港への入港を拒否されたために行き場を失いカリブ海上をさまよっていた複数の外国クルーズ船をブリッジタウンのディープ・ウォーター・ハーバーに受け入れ、数千人の多様な国籍の乗客・乗員をバスで空港までピストン輸送してチャーター機で国に帰すという離れわざを演じたのです。
(これがクルーズ船運航各社に恩を売ることになり、コロナ後のインバウンド観光におおいに寄与することになったのは言うまでもありません。)
ワクチン接種などの国内コロナ対策が効率的に行われたので、国内での流行はさほどひどくはなりませんでした。ここでモトリーはさらに名案を思いつきます。彼女は、コロナ禍によって世界各地でリモートワークが盛んになったことに着目しました。
「どうせオンラインで仕事をするのなら薄暗い自宅にいても陽光豊かなリゾート地にいても同じでしょう。だったらご家族も一緒に1年間の滞在ビザを簡単な手続きで出しますからこのバルバドスで仕事とバカンスを同時に楽しみませんか」といって、欧米富裕層向けの「ウェルカム・スタンプ」という新しいワーケーション・ビザ制度を始めたのです。似たような試みをした国はいくつかありましたが、筆者の知るかぎりではバルバドスが最初でした。
そしてこの国が、イギリス女王(当時)を元首とする立憲君主制から1年をかけて共和制に移行するという宣言をしたのは、まさに世界がまだコロナ禍の真っ最中にあった2020年9月のことでした。筆者などは「よりによってこんな時期に大丈夫かいな?」と思って見ていたのでしたが、モトリー首相が持ち前の指導力で国内世論をまとめ、独立55周年にあたる2021年11月30日にバルバドスが世界でもっとも新しい共和国となった経緯については本シリーズの冒頭でくわしく見たとおりです。一国の国体が平和裡に、かつ秩序だって変更された現場に居合わせることができたのは、筆者にとっても外交官冥利に尽きるできごとでした。
ブリッジタウンの各国外交団の中で「ひょっとすると、このモトリー首相という政治家はただ者ではないのではないか?」という声が出始めたのはこの頃です。
案の定といいますか、彼女はそのご国際的な舞台で次々と新機軸を打ち出し、そのすぐれた発信力でグローバル・サウスの新しいリーダーのひとりと目されるようになっていきます。
2021年10月にスコットランドのグラスゴーで開かれたCOP26(国連気候変動枠組条約第26回締約国会議)で、気候変動の影響を受けやすい小島嶼国の代表として、モトリーが「2°Cの気温上昇は途上国にとっては死刑宣告に等しい」と訴えたスピーチは大きな反響を呼び起こしました。毎回のCOPでの発信が注目を浴びるようになった彼女は、2023年のドバイCOP28では「途上国には気候変動における先進国の責任を追及する権利がある」とも述べています。
彼女は、2022年9月には世界に向けて「ブリッジタウン・イニシアティブ」を提唱しました。これは、気候変動や自然災害に脆弱な国々への支援のため、世銀をはじめとする国際開発銀行(MDBs)改革の一環としてIMFの特別引出権(SDR)の活用などによって新たな資金メカニズムを構築し、中所得国をふくむ脆弱国の取組みを支援するという構想です。この構想は、翌年6月にパリで開催された「新たな国際開発資金取り決めのための首脳会合」でも重要テーマのひとつとなりました。
国際的な場でのこうした活躍で、モトリーは2022年、アメリカ「タイム」誌の表紙をかざり同誌の「世界でもっとも影響力のある100人」に選ばれました。また同年のイギリス「ファイナンシャル・タイムズ」誌では「世界でもっとも影響力のある女性25人」に選出されています。人口30万にも満たない小さな島国の首相としては異例のことと言えるでしょう。

(ミア・モトリー首相)
2023年9月の国連総会におけるスピーチでミア・モトリー首相は「安全保障理事会でウクライナについて真剣に取り上げるのと同様に、気候変動についても取り上げてほしい。世界全体でより多くの人命が脅威にさらされている」と語りかけました。
筆者には、モトリーの呼びかけは気候変動を例として引き合いに出しながらも、“欧米の国々 -- 有り体に言えば白人国家群 -- はヨーロッパで起きている不幸な事件については大騒ぎするが、悲惨なできごとは世界中で起きている。より大切なこと、やるべきことは他にもたくさんあるだろう”と言っているように聞こえました。
本稿の主題である「歴史」に立ち戻ってみると、モトリーは2018年の首相就任以来、かつての大西洋奴隷貿易にかかわるレパレーション(補償)問題について積極的な発言を繰り返してきました。
「大西洋奴隷貿易の損害を被った旧植民地諸国は、奴隷制によって富を築いた国々から『善意(good will)の表明』以外なにものも受け取っていない」と主張するモトリーは、2023年12月、母校のロンドン・スクール・オブ・エコノミクスで行った講演で、イギリスがバルバドスに対し4.9兆ドルを補償する義務を負っていると述べたことがあります(註4)。
奴隷制度のレパレーションについては、従来からさまざまな場で議論が続けてこられたのですが、金額の当否はともかくとして具体的な額が一国の政治指導者により公に言及されたのは、これがはじめてではないでしょうか。
モトリーは、この講演のなかで大西洋奴隷貿易と現代世界の人種差別や貧困、不平等の関連性について説き明かしたうえで次のように語りました。
「(レパレーションに関する)対話は困難で時間のかかるものとなるでしょう。私たちは損失の補填が1年、2年いや5年先になっても支払われるなどとは期待していません。富の収奪と損害は何世紀にもわたって続いたのですから。私たちが求めているのは、自分たちの姿を見てほしい、声を聞いてほしい、そして気持ちを理解してほしいということなのです・・・・・沈黙は企てだけに起因するものではありません。沈黙は恥辱から生み出されているのです。私たちの同胞の多くにとり、その恥辱は背負ってゆくのにはあまりに重いものなのです。考えても見てください。背中を鞭打たれるばかりでなく、鼻がそぎ落とされ、顔に焼きごてがあてられたのです。これは1661年にバルバドス議会を通過した奴隷法で合法とされた刑罰でした。いまこの私が主導する名誉と光栄に浴している議会を、です。私たちには歴史を変えることはできません。けれども私たちには間違ったことを直し、人々が息をすることができるようにするという厳粛な責務があるのではないでしょうか」
長いあいだ大国の欲望と恣意に翻弄され他律的に生きざるを得なかったバルバドスは、いま自律的に進む道を模索しはじめています。
<おわり>
*********************************************
(註1) 新型コロナ感染症の世界的流行以前にバルバドスのインバウンド観光客数がもっとも多かった2019年では、空路で約70万人、海路で約85万人、合計すると人口の5倍以上の観光客が同国を訪れました(2021年2月19日付“Weekend Nation”紙)。
また同年のバルバドスのGDPの17.5%、雇用の12%が観光によるものとなっています(世銀)。
(註2) カリコムにはその後1983年までにアンティグア・バーブーダ、ベリーズ、ドミニカ国、セントキッツ・ネービス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、グレナダ、バハマ、イギリス領モンセラートの8ヵ国1地域が参加。さらにこれらの英語を公用語とする旧イギリス領の枠をこえて、95年には旧オランダ植民地のスリナム、2002年には旧フランス植民地のハイチも加わり、現在14ヵ国1地域が加盟しています。
カリコムの事務局はガイアナの首都ジョージタウンに置かれています。
(註3) 東カリブ諸国機構(OECS)は、東カリブ諸国の地域協力を目的に1981年に設立され、カリコムの下部的組織の役割をはたしています。現在、アンティグア・バーブーダ、グレナダ、セントキッツ・ネービス、セントルシア、セントビンセント及びグレナディーン諸島、ドミニカ国の6ヵ国のほか、アンギラ、イギリス領バージン諸島、モンセラートという3つのイギリス海外領土が参加しています。事務局はセントルシアの首都カストリーズ。
(註4) モトリー首相が言及した大西洋奴隷貿易にかかわる補償額は、2023年にアメリカのコンサル企業Brattle Groupが試算・公表した数字を引用したものです。 同企業の試算では、イギリスの補償額はバルバドスをふくむ14の被害国に対し総額24兆ドルとされています。また、スペイン、フランス、オランダの被害国への補償額はそれぞれ、17.1兆ドル、9.2兆ドル、4.86兆ドルとなっています。
(本稿は筆者の個人的な見解をまとめたものであり、筆者が属する組織の見解を示すものではありません。)
*********************************************
*********************************************
2021年12月以降、2年半、18回にわたって(一財)国際協力推進協会(APIC)のウェブサイトに掲載されてきた連続コラム「バルバドス 歴史の散歩道」は、これでおしまいです。
本稿の執筆にあたっては多くの文献を参考にしましたが、主なものは次のとおりです。
“An Outline of Barbados History”, P.F.Campbell, 1974, COT Caribbean Graphics
“Barbados: A History from Amerindians to Independence”, F.A.Hoyos, 1978, Macmillan Education
“Military History of Barbados 1627-2007”, Major Michael Hartland, 2007, Miller Publishing Company
“A History of Barbados: From Amerindian Settlement to Caribbean Single Market”, Hilary McD. Beckles, 2007, Cambridge University Press
“Caribbean School Atlas for Social Studies, Geography and History”, 2007, Longman Group
“Island in the Sun: The Story of Tourism in Barbados”, Henry Fraser & Kerry Hall, 2013, Miller Publishing
“Westminster’s Jewel: The Barbados Story”, Olutoye Walrond, 2015,
“In the Castle of My Skin”, George Lamming, 2016, Penguin Classics
“A to Z of Barbados Heritage”, C.M. Sean Carrington/Henry S.Fraser/John T.Gilmore/G.Addinton Forde, 2020, Miller Publishing
以上のほか、サイト上の信頼するに足ると判断した情報に加えて、バルバドスの2大日刊紙“The Daily Nation”と“The Barbados Advocate”の日々の歴史関連記事も参考にしました。
最後になりましたが、APIC関係者、とくに拙稿の掲載をお許しいただいた故・佐藤嘉恭・前理事長、重家俊範・現理事長、また、掲載について最初に声をかけてくださった島内憲・評議員(元・駐ブラジル日本大使)ならびに佐藤昭治・前常務理事、また編集・構成にご尽力いただいた荒木恵・理事/事務局長ならびに加藤奈美さん、英語版を作成していただいたケイラ・コソヴァックさんに深く感謝申し上げます。
2024年5月
前・駐バルバドス日本大使 品田光彦

WHAT'S NEW
- 2025.10.23 INFORMATION
令和7年度事業計画書・収支予算書を更新しました。
- 2025.10.16 EVENTS
第421回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2025.10.16 EVENTS
太平洋・カリブ記者招待計画2025を更新しました。
- 2025.10.14 INFORMATION
役員一覧を更新しました。
- 2025.10.14 INFORMATION
令和6年度事業報告書・決算報告書を更新しました。
- 2025.10.8 PROJECTS
【APICだより】2024年度「太平洋・カリブ学生招待計画」参加者が大阪・関西万博のスタッフとして再来日を更新しました。
- 2025.9.26 EVENTS
バヌアツにてPICとの初の合同環境セミナーを開催を更新しました。
- 2025.9.22 SCHOLARSHIP
第10期ザビエル留学生と第3期UWI留学生が上智大学/大学院に入学を更新しました。
- 2025.9.19 SCHOLARSHIP
第1期UWI留学生が上智大学大学院を卒業を更新しました。
- 2025.9.18 EVENTS
第420回早朝国際情勢講演会を更新しました。