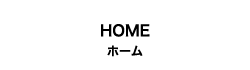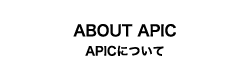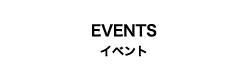「バルバドス 歴史の散歩道」(その10)
第6部 東カリブの要塞島(続き)
(ギャリソン・サバンナ遠景)
<イギリスとフランスの植民地争奪戦>
オランダ艦隊の侵攻を退けたバルバドスは、外敵の脅威にそなえて一層の守りを固めるようになります。ブリッジタウン、ホールタウン、スパイツタウンなど、島の南から西にかけての要衝には多くの砲台をすえた要塞が次々に築かれました。
バルバドスの宗主国イギリスが世界の海でスペイン、オランダを凌駕するようになった18世紀に入ると、植民地獲得競争においてイギリスの最大のライバルになったのはルイ14世治下のフランスでした。
おりしも1701年、ルイ14世がスペイン国王の継承問題に首をつっこんだのをきっかけにヨーロッパ中を巻き込むスペイン継承戦争が始まりました。ヨーロッパ大陸でのこの戦争と並行して、イギリスとフランスはドサクサまぎれに新大陸とカリブ海で植民地争奪を繰り広げます。この戦いは当時イギリスを統治していたアン女王(註1)の名をとって「アン女王戦争」と呼ばれます。戦況はイギリスが優位に進め、北米ではフランス支配下にあったアカディア、ニューファンドランド、ハドソン湾地方などをイギリスが獲得しカナダに地歩を固めたのですが、カリブでの決着は曖昧なままに残されました。
バルバドス近辺の小アンティル諸島だけを見ても、18世紀を通じてセントキッツ、ネービス、グアドループ、モンセラート、ドミニカ、マルティニーク、セントルシア、セントビンセント、グレナダといった島々が目まぐるしくイギリス領になったりフランス領になったりしていて、植民地の奪い合いがいかに激しかったかがうかがわれます。
イギリス艦隊の周辺諸島攻略に際する前進基地になったバルバドスは、ハリネズミのように武装して守りを固めていました。たとえば1730年ごろのバルバドスには、その狭い土地の中に合わせて463門の大砲をそなえた22の要塞があり、騎兵・歩兵は4千人を数えました。
<ギャリソン・サバンナ>
アン女王戦争さなかの1705年、ブリッジタウン郊外のカーライル湾をのぞむ高台に「セント・アン要塞」の建設がはじめられました。この頑丈な石造りの要塞の建設はその後10数年にわたり続いたのですが、ここを中心にして島の軍事施設が整備されていきます。
セント・アン要塞の前は練兵場となり、その周りを囲むように兵舎、武器庫、病院、刑務所などの建物がたてられ、バルバドス植民地の民兵組織――ミリシアの駐屯地(ギャリソン)として使われるようになります。
宗主国イギリスの海軍艦隊は時に応じてバルバドスに来航していたのですが、イギリス軍が島に常駐するようになったのは意外と遅く、アメリカ独立戦争の最中、1780年のことです。「ギャリソン・サバンナ(サバンナ駐屯地)」と呼ばれるようになった広大な練兵場とその周りの建物群は、駐留イギリス軍が1905年の撤退まで東カリブ全域に睨みをきかせる本拠地としての役割をにないました。そして、ブリッジタウンをはさんでギャリソン・サバンナの反対側にあるクイーンズパークには東カリブ方面軍総監の立派な公邸(註2)がおかれました。
のちにバルバドスがイギリスから独立した1966年11月30日、独立記念式典が催されイギリス国旗ユニオン・ジャックが降ろされて新生バルバドスの国旗がはじめて掲げられたのもギャリソン・サバンナでした。
2011年、このギャリソン地区はブリッジタウン旧市街と合わせ、かつて大英帝国がカリブに築いた拠点の姿を伝えるものとして、「ブリッジタウン歴史地区とギャリソン」というタイトルでユネスコ世界遺産に登録されました。そのため、ギャリソンは今もかつての景観をほぼそのまま留めています。主要ないくつかの建物は現在のバルバドス軍の本部に、かつての練兵場は競馬場に、刑務所は博物館に、そしてセント・アン要塞のすぐ下の空き地はなぜか駐車場になっています。
(ギャリソン・サバンナの建物のひとつ「ドリルホール」。1790年に建てられ駐留イギリス軍の兵舎として使われていたこの建物は、現在バルバドス軍の施設になっています)
(現在のセント・アン要塞)
ギャリソン・サバンナのすぐ隣に一軒のコロニアル風建築の館があります。
かつて「ブッシュヒル・ハウス」という名で高級士官の官舎として使われていたこの建物に、のちにアメリカ独立戦争を率い合衆国初代大統領となる若き日のジョージ・ワシントンが1751年11月初旬から6週間ほど滞在していたことがあります。
それで今ではこの館は「ジョージ・ワシントン・ハウス」と名をかえて、クルーズ船来航シーズンなどにはおおぜいの観光客、とくにアメリカ人がワイワイガヤガヤと訪れる、レストラン併設の観光スポットになっています。
ワシントンが一度滞在したくらいでなぜ大袈裟にも名所になっているのかというと、このワシントン、生涯をつうじて北米から外に出たのはたった一度きりで、それがバルバドスだったからなのです。
19才だったワシントンは、異母兄ローレンスと一緒に故郷バージニア植民地から船旅でバルバドスにやってきました。ローレンスは結核を病んでおり、医師に転地療養をすすめられたため、気候温暖なこの島に弟ジョージに付き添われて来たのでした。療養先としてバルバドスが選ばれたのは、かつてこの島にイギリスから移民としてやってきたワシントン家の遠縁の一族が島の名家の一つとなっていたからです。
バルバドスに着いたワシントンは日記にこう書いています。「私たちは、ジェームズ要塞司令官であるクロフタン大尉の家に泊まることになった。家は海に近く、町(ブリッジタウン)からは1マイルほどのところにある。陸と海を広々と見渡せカーライル湾と船の出入りを眺めることができる」(註3)
病身の兄の世話役とはいえ、若きワシントンはラム酒の味もおぼえ、バルバドス生活をそれなりにエンジョイしていたらしいのですが、あろうことか彼は島に滞在中、当時はまだ珍しくない病気だった天然痘にかかってしまいました。軽症ですんだものの顔にはあばたが少し残ってしまったようです。
しかし人生なにが幸いするか分かりません。それから20数年ののち、アメリカ独立戦争の初期にジョージ・ワシントン総司令官が指揮をとる独立派植民地軍の中で天然痘の集団感染が発生します(註4)。多くの将兵がこの病気で命を落としたのですが、かつてバルバドスで天然痘にかかり免疫ができていたワシントンはびくともせず、めでたくアメリカ独立にこぎつけ初代大統領となったのでした。
結核を病んでいた兄ローレンスは、バルバドスからバージニアに戻って数ヶ月後には亡くなってしまったので、彼の転地療養という点ではバルバドス滞在の恩恵はあまりなかったようです。でも、弟ジョージがもしも島で天然痘をもらっていなかったら、その後のアメリカはどうなっていたでしょう?「だからワシントンは大統領就任に際し、祝い酒として樽詰めのバルバドス・ラム酒を注文したのだ」という真偽不明の説(註5)を、筆者はバルバドスで目にしたことがあるのですが、まんざらいい加減な話でもないかも知れません。
真偽不明といえば、もうひとつ。アメリカ独立運動のスローガンのひとつに「代表なくして課税なし」というのがあります。植民地がイギリス議会に代表を送ることが許されないのに植民地住民に課税する法律を議会が作ることへの反感を示す言葉で、その精神はアメリカ独立宣言にも盛り込まれています。ところで、アメリカ独立宣言の120年以上も前にバルバドス植民地と宗主国イギリスが一戦まじえた際の講和文書「バルバドス憲章」(本稿第3部「ピューリタン革命の荒波」)をご記憶でしょうか。憲章のなかには「バルバドス議会の同意なしにバルバドス住民に税を課すことはできない」、つまり植民地と宗主国の関係における「代表なくして課税なし」を意味する条項が入っていました。「若きワシントンは島に滞在中、バルバドス憲章に触れる機会があって、これが彼の頭の中にしっかり刻まれていたのだ」という、なんだか想像力を刺激する説(註6)もあるのですが、どうでしょう?

(ジョージ・ワシントン・ハウス)
北米でジョージ・ワシントンが独立戦争を戦っていた1778年、フランスは仇敵イギリスにダメージを与えるべく13のイギリス北米植民地の側に立って参戦します。
余波はすぐにカリブでの権益争いにも及びました。アメリカ独立戦争への対応のためにイギリスのプレゼンスが手薄になった東カリブ海域では、ドミニカ、セントキッツ、セントビンセント、セントルシア、グレナダなどが次々とフランスの手に落ちてしまいます。この時点でイギリスが死守していたのはジャマイカ、アンティグア、そしてバルバドスでした。苦境に立たされたイギリスは先にふれたように1780年からバルバドスに常備軍を置くようになります。
1782年、フランスはジャマイカ攻略を狙います。これを防いだのはイギリス海軍のジョージ・ロドニー提督でした。ロドニーの艦隊はドミニカ沖での「セインツの海戦」でフランス艦隊に大勝してジャマイカを防衛しました。
その後しばらくの間、この海域でのイギリスとフランスの争いは一時小康状態となったのですが、戦況がふたたび激化する契機となったのは1789年にはじまったフランス革命とそれに続くナポレオン戦争でした。
カリブにおけるフランス革命の影響は、まずイスパニョーラ島のフランス植民地サンドマングであらわれました。
フランス革命が勃発するとサンドマングでは1791年、革命思想に触発されたムラート(白人と黒人のハーフ)と黒人奴隷の蜂起が起きます。当初、反乱奴隷軍を率いたトゥーサン・ルベルチュールはフランス軍に捕らえられ獄死してしまいました。しかし彼の部下たちは、フランス軍に加え、介入してきたイギリスやスペインの部隊とも戦い、長い闘争のすえ1804年、共和国「ハイチ」として独立を達成しました。
世界ではじめて黒人奴隷が自力でなしとげたハイチの独立はバルバドスをはじめ中南米、カリブの多くの植民地に影響を与え、各地の奴隷たちが自由を求める動きにつながっていきます。
いっぽうヨーロッパでは、革命による君主制の動揺をおそれたオーストリア、プロイセンがフランスに介入し、1793年、革命派によってルイ16世が処刑されるとイギリスも参戦しました。
革命の動乱をへてナポレオンが登場するとフランスはヨーロッパ大陸だけでなく世界各地でライバル国、とくにイギリスの植民地に攻勢をかけるようになります。その一環としてナポレオンは、以前の英蘭戦争の時にオランダがしたのと同じように、イギリスの海軍力を分散させるためにカリブで新たな戦端を開きます。
1805年春、ナポレオンの命を受けたピエール・ビルヌーブ提督が率いる18隻からなるフランスの大艦隊がカリブ海に向けて出港しました。
<ネルソンの登場>
ビルヌーブ艦隊を追ってカリブに向かったのは同じく18隻のイギリス艦隊。指揮をとっていたのはホレイショ・ネルソン提督でした。
イギリス史上最高の軍師とされるネルソン提督は1758年、イギリス・ノーフォークに生まれ、家が貧しかったためわずか12歳で海軍に入ります。20代後半にジャマイカやアンティグアに配属され、ネービス島で出会った女性と結婚したりと、彼の人生のいくつかの節目にはカリブとの接点がありました。
ネルソンは海軍での出世街道をあゆみつつ、世界各地の海戦で危険をかえりみない勇猛な闘いぶりで武功をあげたのですが、戦闘で右目と右腕を失い隻眼・隻腕の将校となります。
1798年、ネルソンが「ナイルの海戦」でフランス軍を破り、飛ぶ鳥を落とす勢いだったナポレオンを一時エジプトに孤立させたことで彼の名声は一気に高まりました。ちなみに、このときの戦いでネルソン艦隊の攻撃から命からがら逃げ出したフランス艦隊の指揮官のひとりがピエール・ビルヌーブだったという因縁があります。
さて今回カリブに向かったビルヌーブの艦隊は、バルバドスから240kmほど北にあるフランス領マルティニークに投錨しました。この時点では、ビルヌーブはさらに北のイギリス領アンティグア島に攻撃をしかけるつもりでいたという説が有力です。
追撃してきたネルソンは、ビルヌーブが東カリブの要塞島バルバドスを狙うと考えたのでしょう。ネルソン艦隊はバルバドスのカーライル湾に入港し、ここに停泊して敵を待ちました。
バルバドス島民たちはフランス大艦隊のカリブ来襲の報に接し、いつ攻めて来られるのかと心底びびっていたので、頼りになるネルソンがやってきたのをもろ手をあげて歓迎しました。
ところが、待てど暮らせどビルヌーブ艦隊はやってこない。なんとビルヌーブはアンティグアにも攻め込まず、そのまま大西洋をわたってヨーロッパ近海にもどってしまったのです。
レーダーも人工衛星もない時代のこと、敵の雲隠れを知るよしもないネルソンは、カーライル湾をあとにしてビルヌーブの進路とは逆の南に向かってしまいます。これは、ビルヌーブ艦隊が南のトリニダード島に向かったという誤情報があったためだといわれています。
敵を取り逃したことに気づいたネルソンもヨーロッパ戦線にもどります。数ヶ月後、ネルソン、ビルヌーブ両提督が対峙したのはスペイン・トラファルガー岬の沖でした。ネルソンはここでビルヌーブの艦隊が姿をあらわすのを虎視眈々と待ちかまえていたのです。

(ネルソン提督)
1805年10月21日の「トラファルガーの海戦」は、ネルソン率いるイギリス艦隊がビルヌーブ指揮下のフランス・スペイン連合艦隊を撃破して、ナポレオンのイギリス本土上陸の野望を挫くこととなったとされる、世界史上に残る海戦です。
旗艦「ビクトリー号」で指揮をとったネルソンは、数で勝るフランス・スペイン連合軍を「ネルソン・タッチ」と呼ばれる大胆な戦法――横一線にならんだ敵艦隊の隊列をくずすために自艦隊を縦二列にならべて敵艦隊列の中央に突入する戦法――で破りました。
けれども、安全な場所に身を隠すべきだという部下の助言にもかかわらず甲板上で指揮をとっていたネルソンはフランス艦からの狙撃を受けて落命します。いっぽう、フランス艦隊の司令官ビルヌーブはイギリス軍に捕虜として捕らえられました。
ナポレオンの侵攻から祖国を守り「神に感謝する。わたしは義務を果たした」という言葉を遺して壮絶な戦死を遂げたホレイショ・ネルソンはイギリス救国の英雄となりました。
イギリス本国はもちろんのこと、ほんの数ヶ月前までネルソン艦隊が停泊していたバルバドス植民地の人々は、トラファルガーの海戦の勝利を祝いながらもネルソンの死を深く悼みました。「あのとき提督がカリブに駆けつけてくれていなかったらバルバドスはフランスに乗っ取られていたかもしれない」というわけです。
バルバドスの支配層--裕福なイギリス系移民のあいだではネルソンの功績をたたえるための銅像を建てようという話が盛り上がります。募金が開始されて数週間のうちに当時の金額で2300ポンドが集まり、1813年にブリッジタウンにネルソン像が設置されました。
宗主国の首都ロンドンのトラファルガー広場にも、フランスの方角をにらんで立つネルソンの記念塔があります。これに比べればバルバドスのネルソン像はずっと小振りなものでしたが、バルバドスでの像設置はロンドンのネルソン記念塔が作られるよりも30年以上も前のことです。当時のバルバドスでのネルソン人気がハンパないものだったことが窺われます。
“ナポレオンに一度も負けなかった男“ネルソン提督の像は、こうしてブリッジタウンのシンボルとなったのでした。
ところで、トラファルガーの海戦のあとイギリス軍の捕虜になった敗軍の将、ビルヌーブ提督のその後はと言いますと、彼はイギリス送りになった翌年に釈放されてフランスに帰国しました。しかしまもなくブルターニュの町、レンヌの宿屋で死んでいるのが発見されます。自殺と考えられているのですが、ナポレオンの指示で殺されたのだという説もあります。
歴史にifは禁物ですが、もしあの時ネルソンとビルヌーブがカリブ海で遭遇し交戦していたらヨーロッパ、そしてカリブの歴史は変わっていたかもしれません。
さて、トラファルガーの海戦に敗れたナポレオンはイギリスに報復するため「大陸封鎖令」をしきました。みずからの支配下にあるヨーロッパ諸国とイギリスのあいだの通商を禁止することによってイギリス経済を壊滅させようとしたのです。
大陸封鎖令はしかし、かえってイギリスとの通商に大きく依存していた大陸諸国の経済を麻痺させるというブーメラン効果を生んでしまいました。そのため諸国民のあいだで反ナポレオン感情が高まり、各国の離反をまねいてナポレオンからの解放戦争――諸国民戦争――につながっていきます。
イギリスの耐久力を見誤ったうえに周りの国々の事情をかえりみずに導入した制裁――大陸封鎖令――はナポレオン没落の序章となりました。イギリスももちろんダメージを受けはしましたが、同時にヨーロッパ全体が疲弊し、しまいには現状打開を試みたナポレオン軍がモスクワ遠征に失敗してボロボロになったわけです。こんにち世界で起きていることとの対比で興味深いものがあります。
<シグナルステーション>
何はともあれ、フランスの侵攻から免れたバルバドスでは防衛意識がさらに高まりました。
そこで考え出されたのが「シグナルステーション」と呼ばれる監視塔を島の各地に建設することでした。発案したのは1817年にバルバドス総督になったカンバーミア子爵1世ステイプル・コットンという人物です。従軍経験が長く情報伝達の重要性をよく理解していた総督の指図により1819年までにまず島内6ヶ所の高台にシグナルステーションが築かれました(註7)。
それぞれのシグナルステーションからは周辺の土地と海上が見渡せ、しかも互いが視界に入るように配置されていました。そして、不審船が近づくなどの変事が生じれば信号旗と手旗信号で即座に島じゅうに危機を知らせられようになっていました。シグナルステーションの土地提供と建設・補修は植民地当局、人員配置と運用は駐留イギリス軍が担当するという仕分けでした。
しかし、この物見やぐら――シグナルステーションは外敵からの防衛という目的のほかに、じつはもう一つ大事な役割をもっていました。それは奴隷反乱の未然防止です。
本稿第5部「砂糖、ラム酒、そして奴隷」で紹介したバルバドス史上最大の奴隷反乱「バッサの乱」が起きたのはカンバーミア総督就任の前年のことです。島を揺るがしたこの事件は、黒人奴隷蜂起によるハイチの独立に刺激を受けたカリブ全体の不穏な動きのひとつでもありました。こういった時代背景から、バッサの乱にほとほと懲りていたバルバドスの支配層が奴隷たちの動向への警戒と監視を強めたのは自然なことでした。
現在、かつてのシグナルステーションのうち、島のほぼ中央、セントジョージ教区にある「ガンヒル(文字通り“鉄砲の丘“)」が保存され一般公開されています。そこに登ってみると、たしかに周辺一帯が360度見渡せるようになっていて、望遠鏡を使えば下界の人の集団の動きや砂糖キビ畑の異変などが即座に発見できたであろうということが実感できます。
シグナルステーションにはさらに副次的な用途も生じるようになりました。当時は天然痘、黄熱病、コレラなどがときどき流行しており、兵士が密集するギャリソン・サバンナでこういった伝染病が発生すると、部隊を分散させ一部をシグナルステーションに一時避難させるようになったのです。
こうして島の安全保障に寄与していたシグナルステーションも、やがて世界的にモールス符号や電話が普及しはじめてバルバドスにも導入されると役割はうすれ、19世紀末には使われなくなりました。
(シグナルステーション「ガンヒル」)
筆者がバルバドスに住んでいた2020年11月16日、ブリッジタウン中心部、国会議事堂のすぐ目の前の国民英雄広場に設置されていた、あのネルソン像が政府の決定によって撤去されるという出来事がありました。
像の撤去にさいしてミア・モトリー首相はこう述べました。
「ネルソン像の撤去は単に象徴的な行動にすぎない。この行動は何よりもまず私たちが国の発展において新しい段階に移る用意があるということを示す象徴にすぎないのだ・・・・アイデンティティや文化に関する議論は続けられなければならず、進歩とより良い団結のために、新たな形の奴隷制や差別についての議論もされなくてはならない・・・」
ネルソン像を撤去すべきだという声は、じつはかなり以前、とくに2000年代に入ってからバルバドス国内で大きくなっていました。
かつての黒人奴隷の子孫たちが担う国としてバルバドスが独立して数十年。国民、とりわけ人口の圧倒的多数を占める黒人の多くに「首都のド真ん中に立っていつもオレたちを見おろしているあのイギリス人の像。今のバルバドスにとってあれは一体なんの意味があるの?」という疑問が湧いてきたのです。
ネルソン提督が傑出した軍人であったのは間違いないでしょうが、「大英帝国軍人としてのネルソンは、奴隷貿易と奴隷労働による富で繁栄を謳歌したかつての宗主国の人種差別、植民地主義を体現する人物だ。自分たちや、奴隷にされた祖先たちにとっては、その功績を讃える対象とはなり得ないのではないか」という考え方です。
そういう気持ちの反映なのか、過去数年間、夜間何者かによってネルソン像がペンキで汚されるという事件もときどき起きていました(少なくとも筆者は、実行者が見つかったという話を聞いたことはありません)。
もちろん、像の撤去に反対する声もありました。新聞の投書欄などから拾うと、「ネルソン自身が奴隷貿易にかかわっていたわけではない」、「彼は自分が生きた時代において軍人として当然の義務を果たしただけだ」、「ネルソンがいなかったらバルバドスはフランスの植民地になっていたかも知れないではないか」、「奴隷制が幅をきかせネルソンが活躍していた時代もバルバドスの歴史の一部であり、それを消去することには慎重であるべきだ」といった意見から、「像を撤去すると、気を悪くしたイギリスからの観光客が減るのではないか」(註8)という実利重視の考え方までいろいろでした。
撤去議論のゆくえを大きく左右したのは、2020年5月にアメリカに端を発し世界に波及した「黒人の命も大事だ(ブラックライブズ・マター)」運動の高まり(註9)でした。この運動は黒人国家バルバドスにもインパクトを与え、とりわけ国内のパン・アフリカ主義団体(註10)の行動を活発化しました。この流れのなかで、ネルソン像撤去支持の国内世論が一気に勢いづき、前出の政府決定となったのです。
ネルソン像撤去の当日、周囲ではパン・アフリカ主義団体主催の祝賀行事がありましたが、撤去作業は混乱もなく粛々と執り行われ、200年以上にわたってブリッジタウンの中心部に立ち続けた像は博物館の倉庫へと移されました。バルバドスの歴史にとって一つの区切りとなった一日でした。
(第7部 「奴隷制廃止への道のり」に続く)

(1813年から2020年までブリッジタウン中心部に立っていたネルソン提督像)
(註2)この公邸は「クイーンズパーク・ハウス」と呼ばれ、現在ではギャラリー、小劇場として使われています。
(註3)The Writings of George Washington, vol.1, (1748-57)
(註4)アメリカ独立派植民地軍は一時カナダまで侵攻しイギリス軍をケベックまで追いつめたのですが天然痘の影響もあって進撃が止まりました。ワシントンが頼りにしていたカナダ侵攻作戦の指揮官、ジョン・トーマス少将もこの病気で亡くなっています。その間にイギリス側に援軍が到着したため植民地軍はさらなる侵攻をあきらめ、カナダがアメリカ合衆国の領土に組み込まれることは免れました。
(註5)WEEKEND NATION, January 22, 2021 “US Ambassador toasts Biden-Harris moment”
(註6)The Military History of Barbados 1627-2007 by Major Michael Hartland, p.19
(註7)当初建設されたシグナルステーションは、ガンヒル、ハイゲート、モンクリーフ、コットンタワー、グレネイドホール、ドーバーフォートの6カ所。その後、ブリッジタウンを取り囲むようにさらに5か所に建設されました。
(註8)じっさいにはネルソン像の撤去はイギリス人観光客の数に影響しませんでしたし、バルバドス・イギリス2国間関係を損なうということもありませんでした。
(註9)この文脈でいう「黒人の命も大事だ」運動の高まりとは、2020年5月、アメリカ・ミネソタ州ミネアポリスで黒人男性が白人警官に約8分間にわたり膝で首を押さえつけられて死亡した事件のようすがSNSにより拡散し、抗議活動が世界各地に広がった事象を指します。
(註10)「パン・アフリカ主義」とは、アフリカ大陸の人々および世界のその他の地域のアフリカ系の人々の、抑圧からの解放、権利保障、連帯をめざす運動のこと。
(本稿は筆者の個人的な見解をまとめたものであり,筆者が属する組織の見解を示すものではありません。)
WHAT'S NEW
- 2025.10.23 INFORMATION
令和7年度事業計画書・収支予算書を更新しました。
- 2025.10.16 EVENTS
第421回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2025.10.16 EVENTS
太平洋・カリブ記者招待計画2025を更新しました。
- 2025.10.14 INFORMATION
役員一覧を更新しました。
- 2025.10.14 INFORMATION
令和6年度事業報告書・決算報告書を更新しました。
- 2025.10.8 PROJECTS
【APICだより】2024年度「太平洋・カリブ学生招待計画」参加者が大阪・関西万博のスタッフとして再来日を更新しました。
- 2025.9.26 EVENTS
バヌアツにてPICとの初の合同環境セミナーを開催を更新しました。
- 2025.9.22 SCHOLARSHIP
第10期ザビエル留学生と第3期UWI留学生が上智大学/大学院に入学を更新しました。
- 2025.9.19 SCHOLARSHIP
第1期UWI留学生が上智大学大学院を卒業を更新しました。
- 2025.9.18 EVENTS
第420回早朝国際情勢講演会を更新しました。