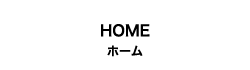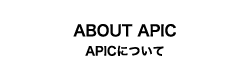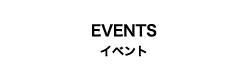「バルバドス 歴史の散歩道」(その9)
第6部 東カリブの要塞島
(バルバドス東岸から大西洋をのぞむ)
バルバドスに住んでいた当時、筆者は船で島の沖合いに出る機会が何度かあったのですが、そのうちあることに気がつきました。時間帯や季節にかかわらず海上の風向きがいつも一定なのです。風向きがくるくる変わる日本近海とはかなり違っていました。
「なるほど、これが東から西に吹いている“貿易風“というものか」と納得すると同時に、バルバドスがなぜ300年以上もの長い期間にわたりイギリスの安定的な支配下にあったのか、その理由のひとつが分かったような気がしたものです。
バルバドスはカリブ海南東部の小アンティール諸島のなかでも、いちばん東にポツンと飛び出したところに位置しています。ここから東側には、アフリカ大陸まで何もない大西洋がひろがっています。バルバドスより西側にあるアンティグア、グアドループ、ドミニカ、マルティニーク、セントルシア、セントビンセント、グレナダといった近隣の島々はどれも、17世紀以降、スペイン、イギリス、フランス、オランダといった国々が取り合いをしていて、しょっちゅう宗主国が変わっていました。けれども、バルバドスだけは1966年の独立まで一貫してイギリスの手中にあり、宗主国が変わったことは一度もありません。
イギリスの植民地だった時代、バルバドスへの軍事的脅威は、しばしばライバル国がおさえている近隣の島々からやってきました。敵の帆船は、バルバドスから見れば西の方角にある自陣の港を出てバルバドスをめざして東進したのです。この時、敵艦隊は、貿易風のために風上にむかって進むことになります。バルバドスを攻撃するためには何回も「帆の上手回し(タッキング)」を繰り返してジグザクに風上に進まなければなりません。これに対して、守るバルバドスの船は常に追い風を受けているため、操船が容易かつ速度もまさっていて、敵船の接近を容易に許しませんでした。
「それなら、バルバドスを攻めるには、島の北か南を大きく迂回して、島の東、大西洋側から攻めればいいのではないか」と思うかもしれません。ところが、バルバドスにとって幸いなことに、大西洋に面する東海岸は波が荒いうえに、浅瀬の岩礁が広がっているので、大きな船が近づくことはできないのです。17世紀前半のイギリス人入植者によるバルバドス開拓がイギリスにより近い東海岸からではなく反対側の西海岸からはじまったのもそのためで、現在でも東海岸にはこれといった港はありません。
帆船が使われていた大航海時代、バルバドスは、敵の攻撃からは守りやすく、逆に近隣の島々を攻略する拠点としては絶好の位置にあったのです。この島が難攻不落の「東カリブの要塞島」となったゆえんです。
現代までの歴史をたどってみると、バルバドス島全体がイギリス以外の勢力によって制圧されたことは一度もなく、海岸線が攻撃に見舞われたのも、①1652年、エイスキュー提督率いるイギリス艦隊が、オランダと仲良くなりすぎたバルバドスを懲らしめるために来襲した時(本稿第3部「ピューリタン革命の荒波」)、②1665年、第2次英蘭戦争中に、ミヒール・デ・ロイテル提督が率いるオランダ艦隊が侵攻してきた時、③1775年に開始されたアメリカ独立戦争中に、北米植民地の私掠船が沖合いからスパイツタウンを砲撃した時、そして④第二次大戦中の1942年、ドイツの潜水艦・Uボート514がカーライル湾停泊中のカナダ貨物船に魚雷攻撃を行った時、の計4回しかありません。
*********************************************
<国際色豊かな島>
バルバドスが過酷な奴隷労働による砂糖の生産と輸出で栄え、カリブ随一のイギリス植民地になると、イギリス人以外の人々も大勢やってくるようになり、島は国際色豊かなコスモポリタン的様相を呈するようになります。
バルバドスを訪れたオランダ人サムエル・コペンが1695年に描いた「ブリッジタウン遠景」というエッチング画には、たくさんの商船が錨をおろすカーライル湾の向こう側に3、4階建ての建物が密集している風景を見ることができます。そして、カーライル湾の南端に突き出したニーダムス・ポイントに砲台をそなえた要塞が集中していることも分かります。コペンが描いたブリッジタウン市街の建物群は、1776年の大火で焼失してしまったのですが、市内の街路は現在もほぼそのままの姿をとどめています(註1)。
西インド諸島各地を探訪したフランス人カトリック聖職者、ジャン=バティスト・ラバは、1700年にバルバドスに立ち寄ったおり首邑の繁栄ぶりにいたく感心したようです。ラバは「ブリッジタウンの街路は長くて清潔である。瀟洒な家々の中にはすばらしい家具が置かれ、商店や倉庫は世界中のさまざまな商品で充ちている。そしてプランテーション領主たちの屋敷は、ブリッジタウンの建物群よりもさらに立派だ」と書きのこしています。
コペンやラバの来訪に先立つ時期、この島にフェルディナンド・パレオロゴスという人物が住んでいました。苗字からピンとくる読者もいるかもしれませんが、この男、ビザンツ帝国最後の皇帝・パレオロゴス朝コンスタンティノス11世の血筋につながるという変わり種です。15世紀半ばにオスマン・トルコに滅ぼされたビザンツ帝国と17世紀のバルバドスのつながりというのも面妖なことですが、これは本当の話です。
パレオロゴス朝の血統は、1454年、オスマン軍の攻撃で首都コンスタンティノープルが陥落しビザンツ帝国が滅亡した時に絶えてしまったわけではなく、その係累はヨーロッパ各地に散らばりました。そのなかで、コンスタンティノス11世の弟の一族がイタリアを経てイギリス・コンウォールに流れ着き、フェルディナンド・パレオロゴスは1619年にそこで生まれたのです。
ピューリタン革命中の1645年。ネイズビーの戦いでクロムウェル軍に王党派軍が敗れると、王党派に属していたフェルディナンドはバルバドス植民地に逃れました。ラストエンペラーの血筋に連なるこの人物は、島で砂糖キビ・プランテーションを拓いて成功します。そして、長年にわたり島東部セント・ジョン教区の英国国教会の世話人をつとめるなどして名士の一人となりました。彼は「コーンウォールから来たギリシアのプリンス」という愛称で親しまれ、この島で平穏な一生を送ったということです。
こんにち、セント・ジョン教区にはフェルディナンド・パレオロゴスが住んでいた「クリフトン・ホール」というプランテーション・ハウスが残っていますし、大西洋をのぞむセント・ジョン教会の墓地を訪ねると彼の墓標を見出すことができます。

(サムエル・コペンが描いた17世紀末のブリッジタウン)

(セントジョン教会の墓地にあるフェルディナンド・パレオロゴスの墓)
バルバドス植民地の発展には、ユダヤ系の人々も一定の役割を果たしました。
本稿第5部「砂糖、ラム酒、そして奴隷」で、17世紀前半にバルバドスに砂糖キビ栽培を紹介したのがオランダだったことに触れました。そのおり、バルバドスの農民に砂糖の製法やアフリカ人奴隷労働の利用について指南した人々のなかには、多くのユダヤ系オランダ人が含まれていました。
ユダヤ人たちはどんないきさつでバルバドスにたどり着いたのでしょうか。
前出のビザンツ帝国が滅んだのとちょうど同じころ、ヨーロッパの西の反対側、イベリア半島でも大きな動きがありました。そのころ、長い間イスラム教徒の支配下にあったイベリア半島でキリスト教徒による国土回復運動(レコンキスタ)が完遂し、スペインやポルトガルの隆盛へとつながります。しかし、そこではキリスト教徒によるユダヤ人迫害がひどくなったため、大勢のユダヤ人がイベリア半島外に逃れるようになります(彼らは「セファルディ系ユダヤ人」と称されます)。その一部は流浪のすえに、宗教に寛容なオランダの影響力が強かった南米のスリナムや、レシフェを中心とするオランダ領ブラジルに定住しました。1630年代末期にはレシフェの人口約1万人のうち、かなりの割合をユダヤ系が占めていたといわれます。
ユダヤ人たちの中には、南米の地で砂糖キビ・プランテーションを経営した者も多くいました。彼らはベネズエラの沖合いにあるオランダ領キュラソー島をアフリカ人奴隷の取引き基地として使い、カリブのほかの島々にも砂糖生産技術と奴隷労働の利用を伝播しはじめたのです。
ところが、オランダの影響下にあったブラジル北東部でポルトガルが反撃に転じると、ブラジルからのユダヤ人流出がはじまりました(オランダ領ブラジルは1654年に消滅)。さらに、スリナムや、カイエンヌを中心地とするフランス領ギアナからも不安を感じたユダヤ人が出ていくようになります。どうもこのころはポルトガル、スペインといったカトリック圏の方がプロテスタント圏よりもユダヤ人迫害の傾向が強かったようです。
こうして流出したユダヤ人のなかにはオランダ本国などヨーロッパに戻った人たちも多かったのですが、一部はバルバドスやジャマイカなど、カリブの島々に活路を見出しました。
ただ、面積が限られているバルバドスでは、この頃にはもう新しいプランテーションを拓けるほどの土地はほとんど残っていませんでした。そこで、ユダヤ人は商店を経営したり貿易に従事したりすることとなります。ブリッジタウンやスパイツタウンにはユダヤ人街が形成され、ことにブリッジタウンでは世帯数の一割以上がユダヤ系になった時期もあります。彼らの商店が軒を並べる市中心部の通りは「ユダヤ人通り」(註2)と称されるようになり、市内にはユダヤ教会(ニデ・イスラエル・シナゴーグ)も建てられました。
1661年にユダヤ系商人の組合が植民地当局から、スリナムと直接交易をする許可を取りつけたこともあって、彼らの経済力はいっそう高まりました。スリナムはユダヤ系の多くにとって元の居住地だったので、人脈や土地勘があり商売に好都合だったと考えられます。
けれども、こうしてしだいにユダヤ人が豊かになっていくのを忌々しく思う人たちがいました。バルバドスの主流を占めるイギリス系入植者たちです。1668年には、ユダヤ人が貿易を行ったり奴隷を買い取ったりすることが法律で禁止されてしまい、さらにはブリッジタウンのゲットー内に住むことが義務づけられます。
かくしてバルバドスでも始まった差別にもかかわらず、18世紀を通じてユダヤ人人口は少しずつ増えていました。このころまでは好況な砂糖産業のおかげで島の経済が豊かだったので、商才に長けた彼らが生き延びてゆくだけの余地があったためでしょう(註3)。
<橋頭堡としての島>
カリブの島々が製糖業で活況を呈しヨーロッパにとって「カネのなる木」であることが分かってくると、各国による領土争奪戦が激しくなったので、バルバドス植民地が自衛しはじめたのは自然の成り行きでした。
イギリスによる植民地化以降、バルバドスには「ミリシア(民兵組織)」と呼ばれる入植者から成る武装組織があり、島内の治安維持や外敵からの防衛に当たっていました。ミリシアの構成員は、初めのうちは志願制だったのですが、1652年に一定以上の土地所有者は家族から一人と馬一頭を供出することが義務付けられます。ミリシア各部隊の指揮はイギリスの職業軍人経験者が担い、敵の船が島に近づくと数百人から数千人規模のミリシアが動員されました。
バルバドスに宗主国イギリスの正規の海軍船がはじめてやってきたのは、ジョージ・エイスキュー提督率いる艦隊がバルバドス討伐のために来襲した1651年でした。次にイギリス艦隊が来たのは1655年で、この時には宗主国の友軍として来航しました。艦隊を率いていたのは、ウィリアム・ペンという提督でした。16隻から成るペン艦隊は、スペイン領だったジャマイカとイスパニョーラ島(現在のハイチとドミニカ共和国)の攻略にむかう途中、バルバドスに立ち寄ったのです。
艦隊はバルバドスで追加兵員を募ったあと北上しました。そして、イスパニョーラ島攻略には失敗したものの、ジャマイカを事実上占領することに成功します。ジャマイカはその後、1670年のマドリード条約でスペインからイギリスに明け渡され、正式にイギリス領となりました。
このようにして、バルバドス植民地はイギリス艦隊が西インド諸島海域の自国領の島々を防衛したり、ライバル国がおさえている島々を襲う遠征途上に兵員や物資を補給したりするための前進基地として使われるようになります。カリブにおけるイギリス進出の橋頭堡となったこの島は、艦隊への食糧や物資の補給、労役用の黒人奴隷の提供で、大いに儲けるようになります。
<オランダとの抗争>
いつの時代でも国際社会におけるスーパーパワーというのは、挑戦者が現れれば、あらゆる理屈と手段を使って潰しにかかります。このことがしばしば当事国間の制裁の打ち合い、時として戦争につながり、小さな国々が巻き込まれて「とばっちり」を受けることになります。
バルバドスが宗主国以外の国の軍事的脅威に初めてさらされたのは英蘭戦争中のことでした。
英蘭戦争は、17世紀後半の3次(1652〜54、65〜67、72〜74年)にわたる戦争で、両国の海軍がドーバー海峡、北海、地中海、大西洋、カリブ海といった広い海域で戦いました。戦争のきっかけは、オランダの海上商業利権を阻むためにイギリスが導入した航海法です。
海上交易を急速に発展させたオランダは、ヨーロッパや新大陸だけでなくアジアにも進出し、世界での海上覇権確立の途上にあったイギリスをイラつかせるようになります。オランダが各地のイギリス市場に食い込んでゆくにつれ、自尊心を刺激されたイギリス国内の反オランダ感情が高まりました。この時、イギリスを治めていたのはピューリタン革命の指導者オリバー・クロムウェルで、イギリスは一時的に共和政の国になっていました。
イギリスは、かねてから海軍のほかに王室の認可を受けた私掠船も動員し、旧勢力であるポルトガルやスペインの縄張りを荒らして勢力範囲を拡大してきました。つまり「強い者が稼いで何が悪いの?」という、ある種「自由貿易主義」的な理屈にもとずいて経済圏を広げてきたわけです。ところがオランダの挑戦を受けたイギリスは、1651年、オランダを標的にした航海法を導入します。つまり、自由貿易で成長してきたイギリスが、今度は一転して、自国の植民地における貿易からオランダ船を締め出すというきわめて保護貿易主義的な措置――今でいう「一方的制裁」――という手段に出たわけです。
ピューリタン革命によるイギリスの混乱にも乗じて漁夫の利を得ていたオランダは「自由貿易」を主張して反発します。この後、イギリスの海軍船や私掠船がオランダ船を拿捕したり、頭にきたオランダ側が挑発的な行動をとったりしたりが続きます。そして、1652年、ドーバー海峡での偶発的な衝突をきっかけに第1次英蘭戦争の火蓋が切って落とされました。
一連の海戦では双方勝ったり負けたりが繰り返されたのですが、イギリス優位のうちにオランダがイギリスの航海法を認めて第1次戦争は収まります。
オランダとの講和のあと、クロムウェルは間髪をおかずにカリブにおける旧敵スペインへの攻撃を強化しました。カリブ遠征を命じられたペン提督の艦隊がスペインから武力でジャマイカを奪い取ったのは前述のとおりです(註4)。
<オランダ艦隊の侵攻>
バルバドスが「とばっちり」を受けたのは、第2次英蘭戦争の時でした。
イギリスはクロムウェルの死後、王政に戻りましたが、オランダとの火種は絶えず、北米のオランダ植民地・ニューアムステルダム(現在のニューヨーク)にイギリスがちょっかいを出したのがきっかけで第2次戦争が始まりました。この時はイギリスのもう一方のライバル、フランスがオランダと同盟を組んで参戦したため、イギリスは苦戦を強いられます。
バルバドスに攻めてきたのは、それまで多くの海戦で武功をあげてきたオランダの提督ミヒール・デ・ロイテルが率いる艦隊でした。第2次戦争が始まった時、デ・ロイテルの艦隊は地中海を航行中だったのですが、本国の指導者ヨハン・デ・ウィット(註5)にカリブ行きを命じられます。イギリスのカリブ植民地を荒らして、後方からイギリスを撹乱するという作戦です。12隻からなるデ・ロイテル艦隊は途中、西アフリカのイギリス要塞を攻撃してひと暴れしたあとカリブ海に向かいました。
1665年4月29日、バルバドス沖に到達したデ・ロイテルは、まず大西洋側から島の東部に砲撃をくわえます。バルバドス上陸を意図していた彼は、岩礁に囲まれた東岸には接近できないことを見てとると、翌朝、島を南から迂回してカーライル湾に向け舵をとりました。
しかし、バルバドスを防衛するミリシア部隊は、敵がこの要衝に来ることを予想して準備を整えていました。デ・ロイテル艦隊がカーライル湾内に突っ込んできたその時、停泊していた商船約20隻と陸上の砲台から一斉砲撃が開始されたのです。湾で待ち構えていた、ただの商船に見えていた船はみな、実は大砲をそなえた武装商船だったのです。
デ・ロイテルが乗った旗艦「シュピーゲル号」は、ニーダムス・ポイントから発射された砲弾の直撃を受けて大きく損傷します。他の多くの船も被害を受けたため、艦隊は退却を余儀なくされました。バルバドスを防衛するミリシア兵たちは、去ってゆくオランダ艦隊にむかって「二度と帰って来るな」と叫んだということです。そして、実際にデ・ロイテルがバルバドスに戻ってくることは二度とありませんでした。
(オランダ海軍提督ミヒール・デ・ロイテル)
その後ヨーロッパ戦線に戻ったデ・ロイテルは、テームズ川の河口まで迫ってイギリスに冷や汗をかかせ、また、つぎの第3次戦争ではオランダ侵攻を企てたイギリス・フランス連合艦隊(註6)を何度も撃退して救国の英雄となります。そして、英蘭戦争終結後の1676年、仏蘭戦争中に地中海シチリア沖で戦われた「アウグスタの海戦」で彼が戦死した際には本国で国葬が営まれました。
後世、オランダ海軍の軍艦に「デ・ロイテル」という名が冠せられたことや(註7)、オランダがEU通貨ユーロを導入する前に使用されていた100ギルダー紙幣に彼の肖像画が使われていたことからも分かるように、ミヒール・デ・ロイテルはオランダ史に残る海軍提督です。
デ・ロイテル艦隊がバルバドスを攻めた時、大西洋を渡っての長征で消耗していたであろうことを差し引いても、オランダが誇る名将の攻撃を自力で退けたこの時のバルバドスを誉めてあげてもよいのではないでしょうか。
筆者は、バルバドスがこの戦いのあと長いあいだ敵の攻撃を受けることがなかったのは、デ・ロイテルを撃退したことによって、この小さな島を攻略するのは容易でない――「下手にバルバドスに手を出すと火傷をする」ということが列国に知れ渡ったからではないかと思うのです。
3次にわたった英蘭戦争は1674年に終結しました。英蘭戦争の結果については「イギリスが勝利した」と説明されることが普通なのですが、イギリスがオランダ国内まで侵攻したわけではなく、双方が疲弊し軍事的には中途半端な終わり方でした。しかし、この長い戦争でオランダの軍事・経済力が打撃をうけ、その後の世界の海における覇権争いでイギリスが主導権を握りスーパーパワーとなった一方、オランダが脱落してミドルパワーの道をたどることにつながったのは間違いないようです(註8)。
(第6部「東カリブの要塞島」は次回に続きます。)
(註1)コペンのエッチング画に描かれたニーダムス・ポイントには現在、ヒルトンやラディソンといった大型リゾートホテルが建っていて、観光の中心地のひとつになっています。コペン画の写しはバルバドス博物館・歴史協会に今も保存されています。
(註2)「ユダヤ人通り」は現在は「スワン通り」と呼ばれており、ブリッジタウン中心部の庶民的なショッピング・ストリートになっています。
(ブリッジタウンの「スワン通り」。17世紀にはユダヤ人の商店が並び「ユダヤ人通り」と呼ばれていました)
現在のバルバドスには、ごく小さなユダヤ人コミュニティーが存在しますが、この人たちは第2次世界大戦期、ナチスによる迫害を逃れてヨーロッパから移住してきたアシュケナージ系ユダヤ人です。セファルディ系がいなくなったあと長いこと打ち棄てられていたニデ・イスラエル・シナゴーグは、ようやく2008年になってアシュケナージ系の人たちによって活動を再開しました。
(註4)ペン提督は、この戦績にもかかわらず、イギリスに戻るとすぐにクロムウェルによって投獄されてしまいました。短期間で釈放されたものの、一時アイルランドに移住。1660年の王政復古になってイギリスへの帰国が叶いました。なお、ペン提督の息子は、のちに北米ペンシルバニア植民地の総督となりフィラデルフィア市を建設したウィリアム・ペンです。
(註5)ヨハン・デ・ウィットは無総督時代のオランダ共和国における事実上の最高政治指導者。のちに内外政の失策により、1672年、兄のコルネリス・デ・ウィットと共にハーグで民衆に虐殺されました。
(註6)フランスは第2次英蘭戦争でオランダ側につきましたが、第3次戦争ではイギリスと「ドーバーの密約」を結んで共にオランダ侵攻を企てました。
(註7)1936年に就航したオランダ海軍の巡洋艦「デ・ロイテル」は、太平洋戦争初期に東南アジア海域で大日本帝国海軍との死闘を繰り広げ、最後は1942年にスラバヤ沖で巡洋艦「羽黒」の魚雷により撃沈されました。
(註8)皮肉なことに英蘭戦争後、1688年に起きたイギリス名誉革命で、イギリスはオランダ総督ウィレム3世をイギリス王ウィリアム3世として迎えることになります。
(本稿は筆者の個人的な見解をまとめたものであり,筆者が属する組織の見解を示すものではありません。)
WHAT'S NEW
- 2026.1.15 EVENTS
第424回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2026.1.14 PROJECTS
インタビュー:田中一成 APIC常務理事(前駐マーシャル諸島共和国特命全権大使)を更新しました。
- 2026.1.14 SCHOLARSHIP
ザビエル奨学金卒業生のインタビュー記事が在パラオ日本国大使館のホームページに掲載を更新しました。
- 2025.12.18 EVENTS
第423回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2025.11.20 EVENTS
第422回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2025.11.19 EVENTS
西インド諸島大学モナ校学長招待計画を更新しました。
- 2025.10.23 INFORMATION
令和7年度事業計画書・収支予算書を更新しました。
- 2025.10.16 EVENTS
第421回早朝国際情勢講演会を更新しました。
- 2025.10.16 EVENTS
太平洋・カリブ記者招待計画2025を更新しました。
- 2025.10.14 INFORMATION
役員一覧を更新しました。